労働組合によるワークライフバランス改善の進め方。組合員の声から環境を変えるには
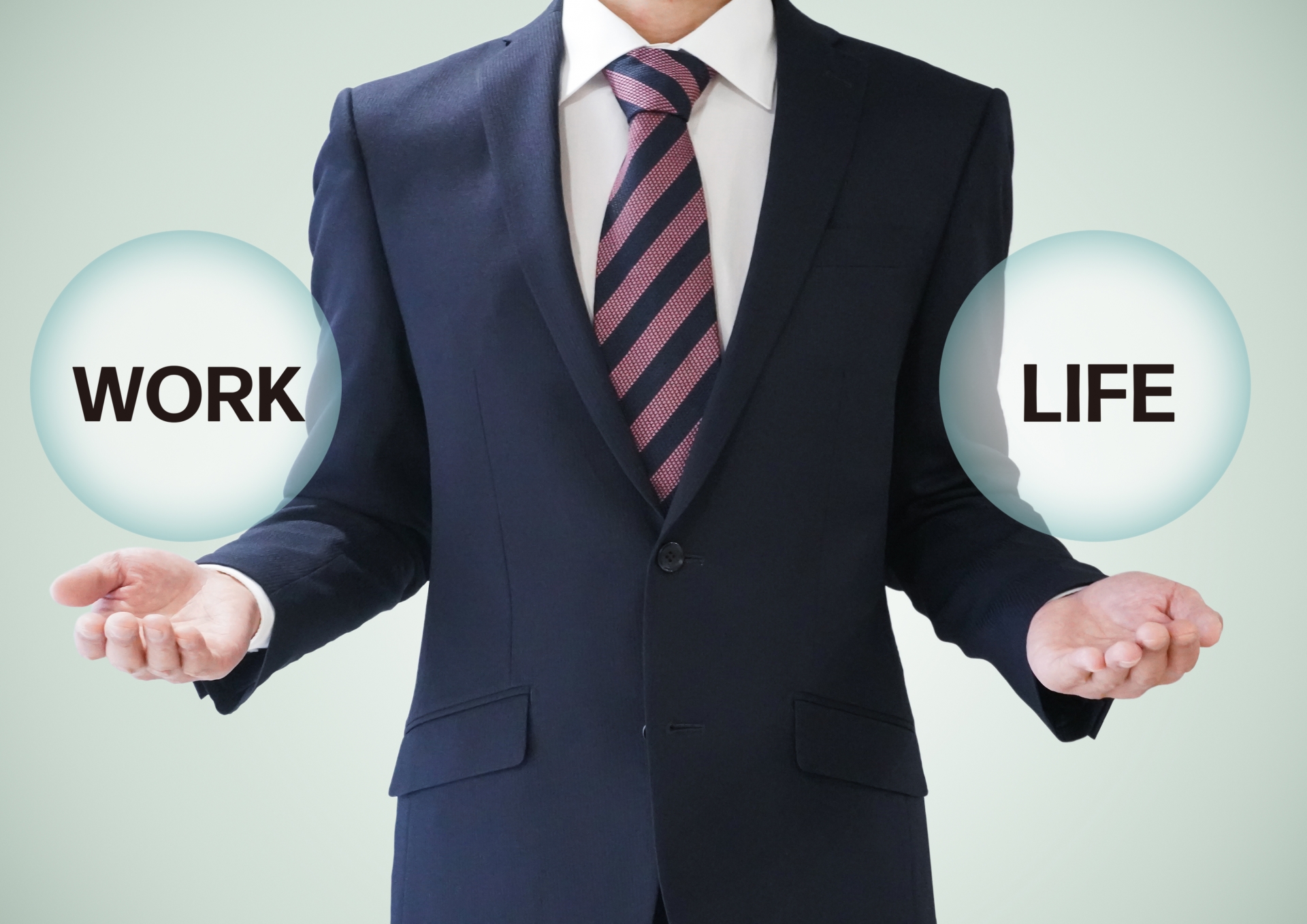
ワークライフバランスの問題は、労使交渉で後回しにされがちです。しかし仕事と生活を両立できない働き方は、労働者に悪影響を及ぼします。組合としてワークライフバランス改善を求めるべき理由や、組合が仕事とプライベートを両立できる環境づくりのために取れる行動を解説します。
なぜ労働組合がワークライフバランス問題に向き合うべきなのか
ワークライフバランスとは、労働者が仕事とプライベートの調和を取り、そのどちらも充実させられる働き方や生き方です。単に労働時間を短くすることがワークライフバランスの実現ではありません。
育児や介護に関する制度を使える、周囲の理解を得てサポートを得られることも、ワークライフバランス実現に必要な状態です。労働組合は、長時間労働の問題や職場の制度・環境整備について、課題があるなら使用者に改善を求める必要があります。
労働組合の使命は労働環境や待遇の改善を目指すこと
労働組合法では、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」を目的として労働組合の活動が認められています。労働組合は労働時間や休日・育児や介護との両立など、ワークライフバランスに関する課題に対応する使命を持つ組織です。
ワークライフバランスは、労使交渉で賃金や安全衛生ほど重視されないかもしれません。しかし、実際に春闘で取り上げられることもある重要な労使交渉テーマです。
ワークライフバランスの悪化は労働者にとって大きな問題
労働者は組織にとって重要な労働力であると同時に、家事や育児・介護・地域活動など、仕事以外にも重要な生活時間を持つ「人間」です。ワークライフバランスの実現において、「ディーセント・ワーク(人間らしい働き方)」という概念は欠かせません。
例えば労働力として酷使されて長時間労働が続くと、趣味や休養の時間を取れず、メンタル不調や過労死のリスクが高まります。育児や介護に関する制度の整備不足・形骸化で家庭との両立が困難になれば、労働者の家庭環境が悪くなります。
これでは人間らしい働き方とはいえないでしょう。ディーセント・ワークが実現しない環境は、離職や少子化といった、企業や社会にとっての問題にもつながります。
国や関係団体の合意に基づく取り組みも進んでいる
2007年に政府・労働組合・経済団体・自治体のトップが「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」とその行動指針に合意しました。
行動指針には、「仕事と生活の調和が実現した社会」に必要とされる諸条件や、企業や労働者・国民・国・地方公共団体それぞれが主体となって取り組むべき事柄が示されています。
企業には、経営トップを筆頭に柔軟な働き方の実現、職場の悪い風土を改善するための意識改革に取り組むことが求められています。労使双方でワークライフバランスの実現に向け、業務の進め方や従業員それぞれのスキル向上などによって時間当たりの生産性を高めることなども、行動指針に示されている事項の1つです。
ワークライフバランスを実現するための行動は、企業(使用者)だけに求められているわけではありません。労働組合を筆頭とした労働者サイドも、仕事と生活を調和させた働き方に向けて動かなければならないのです。
参考:仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章 – 「仕事と生活の調和」推進サイト – 内閣府男女共同参画局
参考:仕事と生活の調和推進のための行動指針 – 「仕事と生活の調和」推進サイト – 内閣府男女共同参画局
ワークライフバランス実現に向けて労働組合ができる協議のポイント
組合員から「育児との両立が難しい」など、ワークライフバランスが実現できていない状況の報告があった場合、労働組合は何をすればよいのでしょうか。使用者と建設的な協議をするために、必要なポイントを解説します。
組合員の声を拾って現場の課題を整理する
育児・介護の支援制度や休暇制度はあっても、実際には活用されていないという現場も少なくありません。ワークライフバランスの問題に対応するには、実際に現場で働いている組合員の声を拾ってリアルな実態を把握する必要があります。
声を集める方法の例は、春闘アンケートや支部会議などです。少数でも切実な声を拾い、協議の中で扱うことで使用者の共感を得やすくなり、改善される可能性が高まります。
法制度も踏まえて協議の説得力を高める
ワークライフバランス実現に向けた協議の際は、組合員から収集した声に加え、関連法令・制度も根拠として添えましょう。協議を感情的な対立ではなく、論理的な対話にできます。
例えば労働時間に問題があるなら、「36協定を結んでいても上限は原則月45時間・年360時間まで」といった法的な定めや、厚生労働省が発表している長時間労働による健康被害のリスクなどを資料に取り入れるとよいでしょう。
ただ、ワークライフバランスの実現には複数の法律が関わってきます。労働基準法や労働安全衛生法、育児・介護休業法など、関連法令の知識を網羅しておかなければなりません。
TUNAG for UNIONをワークライフバランス改善提案の準備に活用
ワークライフバランス実現のために使用者と協議する際、準備に使えるツールに労働組合向けのアプリ「TUNAG for UNION」があります。準備の具体的なイメージをつかむためにも、どのように活用できるのかを見てみましょう。
アンケートでワークライフバランス関するニーズを可視化する
TUNAG for UNIONは情報の発信・共有だけでなく、アプリ内でアンケートを実施することも可能です。特に育児中・介護中の組合員など、ワークライフバランスの実現を願う層の希望や実態を把握するのに役立ちます。
現場の声を拾うことで、ワークライフバランスについて協議すべき課題が明確になるでしょう。制度はあるが使えていない、知られていないというギャップの把握もスムーズになります。
法制度の共有で組合内の知識を底上げする
国や使用者がワークライフバランスを実現するための制度を用意していても、組合員が正しく認識していないケースもあるでしょう。利用条件や手続きに誤認があると、制度が形骸化しやすくなってしまいます。
TUNAG for UNIONを活用することで、制度内容を常時確認できる仕組みをつくれます。組合全体の知識レベルが上がれば、結果として正しく制度を活用できたり、企業に正当な交渉をしたりできる従業員が増えます。
労働組合向けアプリ – TUNAG for UNION|情報共有、申請手続きをペーパーレス化
労働組合の行動がワークライフバランス改善の一歩に
ワークライフバランスは、労働者が人間らしく働き・生活するために欠かせない概念です。仕事もプライベートも充実した生き方には、適正な労働時間はもちろん、制度の充実や実際に制度を使える環境の整備が求められます。
労働組合は、労働者の労働条件を維持・改善するための団体です。ワークライフバランスに関する懸念が組合員から上がったら、課題やニーズを把握した上で、使用者との交渉に臨みましょう。











