就業規則とは?他の労働関連ルールとの違いや労働組合との関係を解説
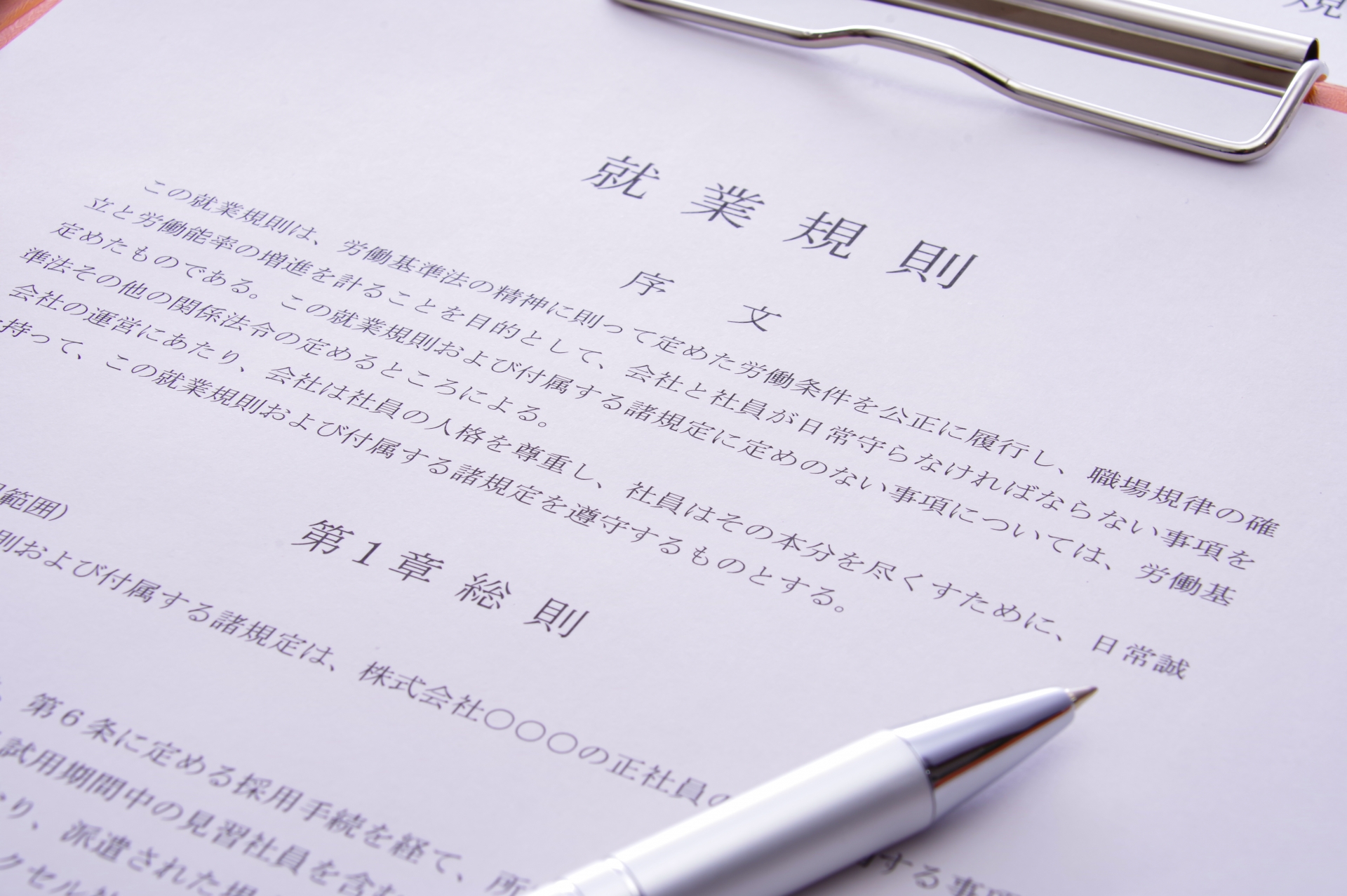
常時10人以上の従業員を雇用する企業には、就業規則の作成・届け出が義務付けられています。就業規則を変更する際は労使間の話し合いを求められているため、労働組合としても理解を深めておくことが重要です。就業規則の基本と労働組合との関係を解説します。
就業規則の基本
就業規則とは具体的にどのようなものなのでしょうか。まずは、就業規則の基本を押さえておきましょう。
就業規則とは
就業規則とは、従業員の労働条件や服務規律などを定めたルール集のことです。企業と従業員の双方が守るべきルールを、法令や労働協約に反しない範囲で規定します。
賃金・労働時間・休憩時間・休日・退職など、就業規則に記載される内容はさまざまです。就業規則の基準を満たさない労働条件を定めた労働契約は無効となり、その部分は就業規則の基準が適用されます。
出典:就業規則を作成しましょう
就業規則の役割
就業規則があることで労働条件が明確になり、従業員が常に労働条件を確認できるため、安心して働けるようになります。期待される行動が明確になるため、モチベーション向上にもつながるでしょう。
服務規律の明確化も就業規則の重要な役割です。企業が何を許可し何を禁止しているのかが分かりやすくなり、企業側も労務管理の対象を客観的かつ公平に判断できます。
また、就業規則があれば労使間のトラブルを未然に防ぐことが可能です。問題が発生しそうなケースでも、就業規則に立ち返って確認すれば、大きなトラブルへの発展を予防できます。
就業規則の記載内容
就業規則の記載内容には、全ての企業で記載が必須の「絶対的必要記載事項」と、ルールを設ける場合に記載が必須となる「相対的必要記載事項」があります。
- 絶対的必要記載事項:賃金・労働時間・退職に関するルール
- 相対的必要記載事項:退職手当・最低賃金額・安全衛生・教育訓練などに関するルール
企業理念・服務規律・採用・異動・福利厚生など、企業の実情に照らして記載すべきと判断したルールは、「任意的記載事項」として就業規則に盛り込むことが可能です。
出典:就業規則を作成しましょう
就業規則の義務
就業規則には法律でさまざまな義務が課されています。作成義務・届出義務・周知義務の具体的な内容を見ていきましょう。
作成義務
労働基準法第89条では、常時10人以上の従業員が働いている事業所に就業規則の作成を義務付けています。従業員にはパート・アルバイトも含まれることや、企業単位ではなく事業場単位であることがポイントです。
また、閑散期には働く人が10人未満になる場合も、常態として10人以上の従業員に働いてもらっているなら、常時10人以上の従業員を使用する事業所と見なされます。
届出義務
就業規則を作成する際、企業は従業員から意見を聞く必要があります。従業員が就業規則の中身を全く知らないということがないようにするためです。
意見聴取の対象となるのは、従業員の過半数で構成される労働組合があるならその労働組合、該当する組合がない場合は民主的な方法で選出された過半数代表者です。
従業員から聞いた意見は意見書にまとめ、就業規則と一緒に所轄の労働基準監督署へ届け出ます。就業規則の届け出も法律で規定された義務です。就業規則を変更する場合も同様に、意見書の添付と労働基準監督署への届け出が必要になります。
出典:労働基準法 第八十九条、第九十条 | e-Gov 法令検索
周知義務
就業規則の周知義務とは、従業員がいつでも就業規則を見られるようにすることです。周知方法の例としては次のようなものが挙げられます。
- 各作業場の見やすい場所に常時備え付ける、または常時掲示する
- 従業員に書面で交付する
- 磁気テープや磁気ディスクに記録した上で、従業員が常時確認できる機器を設置する
就業規則の周知義務は、労働基準法第106条で規定されているルールです。
就業規則と他の労働関連ルールとの違い
就業規則と似たルールには、労働契約・労使協定・労働協約があります。それぞれの意味や就業規則との違いを押さえておきましょう。
就業規則と労働契約の違い
労働契約とは、会社と従業員の間で個別に取り決めるルールです。雇用契約と呼ばれることもあり、賃金や労働時間といった条件を法律に基づいて規定します。
就業規則は労働契約を優先し、就業規則の基準に達しない労働契約は無効です。例えば、就業規則で所定労働時間を1日7時間としている場合は、個別の労働時間も7時間を上限に設定する必要があります。
ただし、就業規則よりも良い条件が労働契約に盛り込まれている場合、その条件は有効です。就業規則で規定していない手当を個別に適用させるといったケースが挙げられます。
就業規則と労使協定の違い
特定の労働条件について、労使間で法定基準の適用除外を定めたルールが労使協定です。時間外・休日労働に関する協定(36協定)やフレックスタイム制に関する協定などが該当します。
労使協定の主な目的は、労働基準法の例外を定めることです。就業規則は法令にのっとって規定しなければならず、労使協定は法令に定められた例外的な扱いを認めるものであるため、就業規則の特則として労使協定が機能することになります。
就業規則と労働協約の違い
労働協約とは、労働組合と企業の間で締結される取り決めのことです。団体交渉で決定した賃金や労働条件などに関するルールを定め、双方が書面に署名または記名押印することで効力が発生します。
労働協約ではさまざまな項目を定めることが可能です。労働者の待遇に関する基準を定めた規範的部分と、労使関係について定めた債務的部分に大きく分けられます。
就業規則が全従業員に適用されるのに対し、労働協約の適用範囲は原則として組合員のみです。ただし、一定の条件を満たしていれば、組合に加入していない従業員にも拡張して適用されます。
就業規則と労働組合の関係
労働組合として特に押さえておきたい就業規則との関係を解説します。組合の活動にも大きく影響する可能性があるため、しっかりと理解しておきましょう。
労働協約は就業規則に優先する
企業と労働組合の団体交渉で締結される労働協約は、就業規則に優先します。就業規則は会社主導で決定されるものである一方、労働協約は労使間の徹底した話し合いで決まるものであるためです。
また、労働協約は個別の労働契約にも優先します。会社と従業員の間で労働条件を決める場合、従業員の立場がどうしても弱くなりがちです。労働協約は労働契約を優先するため、従業員が結束して活動することは、従業員一人一人を守ることにもつながります。
労働組合が会社と対等の立場で話し合って締結できる労働協約は、他のどの労働関係ルールにも優先する、非常に強い効力を持つものなのです。
就業規則の不利益な変更には労働組合の合意が必要
就業規則を変更する場合に、従業員の意見を求める義務があることは前述した通りです。ただし、過半数労働組合や過半数代表者が意見書の提出を拒否した場合も、就業規則の変更は認められます。
従業員にとって不利益な変更になる場合は労働者の合意が必要ですが、そうでなければ会社が従業員に意見を求めたことが証明できればよいのです。
これらを踏まえると、就業規則が会社側である意味勝手に変更されるケースも考えられます。会社から就業規則の変更について意見を求められた場合は、組合員にとって実質的に不利な内容になっていないか、労働組合としてきちんと確認することが大切です。
就業規則を正しく理解しよう
就業規則は、法令にのっとって従業員の労働条件や職場でのルールを定めたものです。職場の決まり事を明確にし、働きやすさを向上させたりトラブルを回避したりする役割があります。
労働組合が就業規則について押さえておくべきポイントは、労働協約が就業規則に優先することと、就業規則の不利益な変更には労働組合の合意が必要であることです。就業規則について理解を深め、今後の組合活動に生かしていきましょう。











