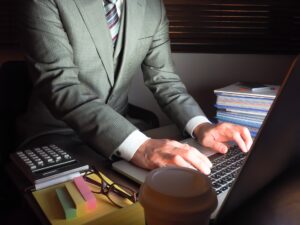労働組合の団体行動権とは?正当性の条件と組合内で備えるべき対応策

労使での交渉がうまくいかず、団体行動に移すべきか悩んでいる労働組合もあるのではないでしょうか。団体行動権は労働組合に認められた権利です。適切に行使して労働環境の改善につなげるためにも、団体行動権の意味や団体行動の正当性、実際に団体行動権を行使するときのポイントを押さえておきましょう。
労働組合に認められた団体行動権とは?
企業と団体交渉をしても協議がまとまらないとき、労働組合が行使できる権利が「団体行動権」です。団体行動権とはどのような権利なのかを、憲法や労働組合法をベースに分かりやすく解説します。
憲法で保障された労働三権の1つ
日本国憲法第28条は、勤労者に「団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)」という「労働三権」を保障しています。労働三権は、労働条件の維持・改善を目的とした労働者側の自律的な権利です。
これらの権利は、使用者との力関係の不均衡を是正し、集団的交渉を可能にするために保障されています。団体行動権は、その中でも「実力行使」を認めた重要な手段と位置付けられます。正当な手続きを経た争議行為(ストライキなど)を通じて、労働条件の改善を実現するための権利です。
参考:日本国憲法 第28条|e-Gov法令検索
参考:労働組合 |厚生労働省
団体行動には正当性が必要
団体行動権は憲法で保障された労働者や労働組合の権利ですが、無制限に認められるわけではありません。例えばストライキを起こしたとき、「正当な争議行為」である場合にのみ、刑事責任・民事責任(損害賠償責任)が免除されます。
労働組合法第1条第2項では、労働組合の正当な団体行動は刑法第35条の「正当行為」に当たるとしています。また同法第8条によると、労働組合がストライキを起こしたことで企業に損害が生じても、正当なストライキであれば組合や組合員は損害賠償の責任を負いません。
正当性の要件は主体・目的・態様です。暴行が伴う争議行為はもちろん違法です。事前の団体交渉が十分でない「即ストライキ」も、不当と見なされる場合があります。
参考:労働組合法 第1条第2項・第8条|e-Gov法令検索
参考:刑法 第35条|e-Gov法令検索
団体行動を理由とする不利益取り扱いは違法
労働組合法の中で第7条は、企業の「不当労働行為」を禁止する条文です。同条第1号には、組合員であることや正当な組合活動を理由に、解雇・配置転換など労働者に不利益な取り扱いをしてはならないと定められています。労働組合への不加入や脱退を条件とした雇用も、いわゆる「黄犬契約」と呼ばれる不当労働行為です。
同条第2号によれば、団体交渉の申し入れを企業が正当な理由なく拒否することも、不当労働行為として認められていません。企業側の行動が不当労働行為に該当した場合、労働組合は労働委員会に対して申し立てができます。
申し立てをしたことを理由に、組合員(労働者)を解雇したり不利益的取り扱いをしたりすることも不当労働行為です(同条第4号)。労働委員会は、不当労働行為の申し立てがあったときは遅滞なく調査し、必要に応じて審問しなければならないとされています(同法第27条第1項)。
参考:労働組合法 第7条第1号、第2号、第4号・第27条|e-Gov法令検索
労働組合が団体行動権を生かすためのポイント
労働組合が団体行動権を生かして、職場の環境・待遇などの改善につなげるには、いくつか注意したいポイントがあります。具体的に何を意識すればよいのでしょうか。
正当性を欠かないよう慎重に判断する
ストライキを含む団体行動には、正当性があるかの判断が不可欠です。正当かどうかを判断するには、団体交渉に対する企業の対応状況も踏まえる必要があります。例えば団体交渉を経ずいきなりストライキを起こすと、不当と見なされる可能性が高いでしょう。
団体行動の中でストライキを例に取ると、正当性が認められるのは次のようなケースです。
- 労働条件の維持や改善を目的としたストライキ
- 労働者の待遇や労働環境に直接影響を及ぼす経営事項に対して改善・変更を求めるストライキ
- 団体行動の拒否に対する抗議を目的としたストライキ
一方で以下のようなストライキは、正当と認められない可能性が高いと考えられます。
- 取締役の選任をはじめとした、労働環境や待遇などに直接関わりのない経営事項について要求するストライキ
- 福利厚生の充実や賃金の引き上げなど、具体的な要求を提示せずに行うストライキ(抗議ストライキ)
労働組合としては、団体行動を要求につなげるためにも目的の正当性について理解しなければなりません。正当とされる団体行動の例を労働組合全体に周知し、組合内での知識の底上げを図りましょう。
団体行動までの経緯を記録して正当性の根拠を残す
ストライキのような争議行為の前に団体交渉がないと、団体行動の正当性が認められない可能性が高くなります。団体交渉の申し入れや交渉経緯は、申し入れの日時や議題・出席者・企業側の対応など詳細に記録しておきましょう。
記録を残すことで、「交渉を尽くしたが要求が認められなかった」という経緯が残り、正当性を確保しやすくなります。合理的な理由のない団交拒否など不当労働行為があった際の証拠になることも、記録を残すメリットです。
組合員と意思統一して進める
団体行動権を行使して労働環境の維持や改善につなげるには、組合内での意思統一も欠かせません。団体行動に対する賛否・懸念をあらかじめ集め、一致団結して団体行動に臨める状態をつくりましょう。
コミュニケーション不足や意見の食い違いがあると、執行部と組合員間に分断が生じて団体行動がスムーズに進みません。団体行動権を行使するには、組合全体が同じベクトルで行動することが重要です。
団体行動権を生かせる労働組合へ
団体行動権とは憲法で保障されている労働三権の一つで、正当性のある団体行動は刑事・民事どちらの責任も問われません。正当と見なされる団体行動の例を理解し、団体交渉の経緯を記録した上で団体行動の準備を進めましょう。
労働組合向けのアプリ「TUNAG for UNION」には、アンケート機能や情報共有を簡単にする機能があります。団体行動に向けての意見収集はもちろん、正当性のある団体行動の基準を共有することが可能です。