【神奈川県高等学校教職員組合】若い世代を大事に、ひとりひとりの組合員と役員との接点を持ち続け、教職員の働き方を変えていきたい。
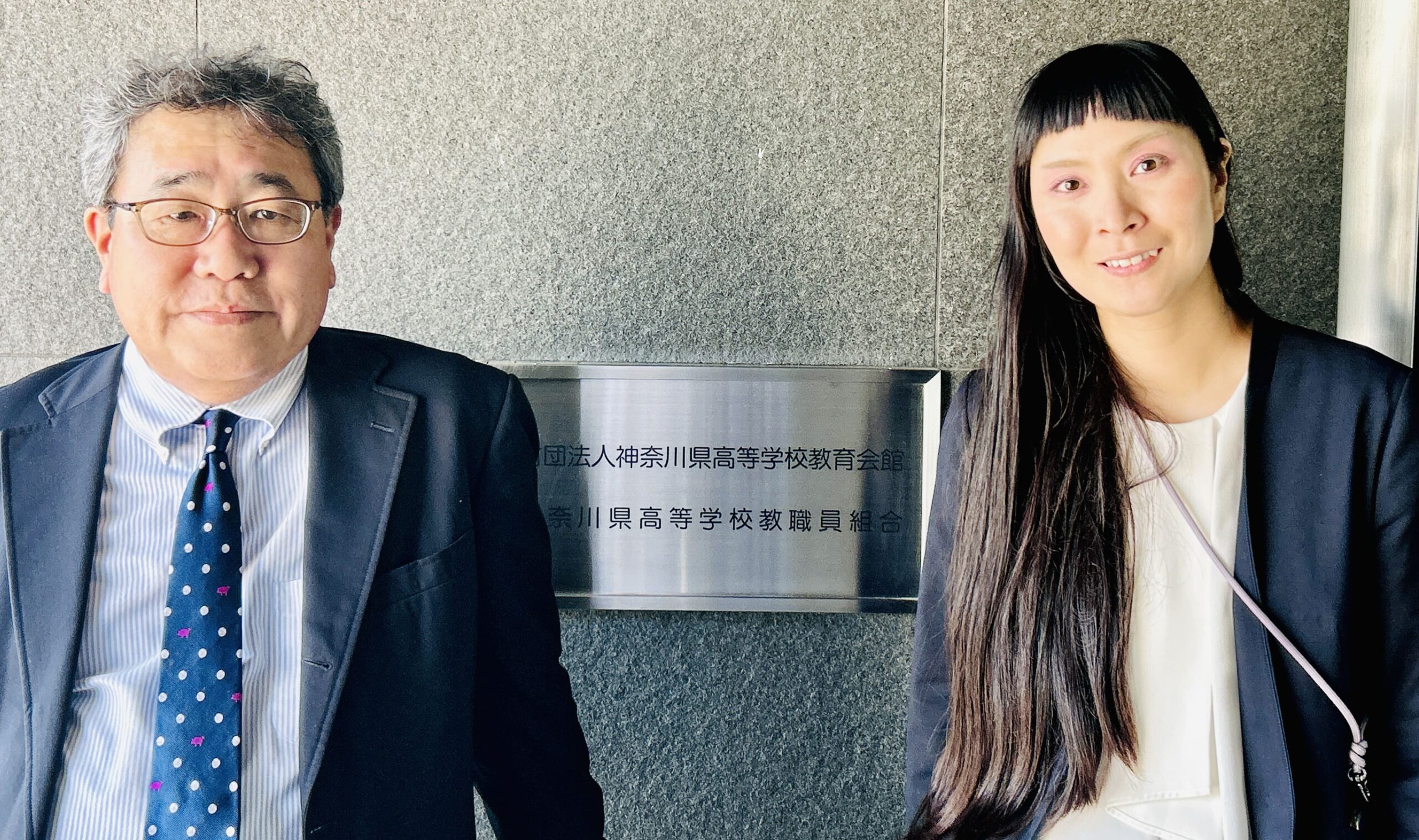
神奈川県の県立高校に勤めている約5,000名の組合員を抱えている、神奈川県高等学校教職員組合様の佐藤(治)委員長と佐藤(彩香)書記長に、現状の課題から未来への想いについて、様々なお話をお伺いしました!(以下、敬称略)
自己紹介や組織概要について
組織概要
佐藤委員長:我々は神奈川県の県立高校に勤めている者で、教員だけではなくて、事務職や養護教諭、現業職員、学校図書館の司書、非常勤職員など、高校で働く人をほぼすべてを対象として組織をしている労働組合で、約5,000名の組合員を抱えています。高校を対象とした教職員組合の中では、一番人数の多い労働組合になります。産別については、日教組に所属しております。
自己紹介
佐藤委員長:私自身は、政治経済の教員で、社会科学系の学部を出ているので、大学時代の周りには教員を目指す人はほとんどいなかったんですね。ただ、高校で最後習った政治経済の授業に影響を受けたこともあり、教員になるという道は、候補の一つとしては考えていました。同時に、6歳上の兄がいて、同じく社会科の教員になろうとしている事もあり、その影響もあって教員を目指そうという気持ちが強くなってきたというところかなと思います。
大学時代の卒業論文も「高校中退者が多い」という問題を取り上げて論文を書きましたが、当時の兄の知り合いを頼って、労働組合の資料を活用していた事もあり、大学時代から労働組合という存在自体に実は接点もありました。その後、就職してからも組合の方と関係があったので、早い段階から組合の各会議に誘ってもらって参加をしてきました。
1989年に採択された子どもの権利条約という条約があるのですが、まだ当時は、日本は批准をしていなかったんですね。それでもすぐに、その子どもの権利条約を批准して、その内容を生かした学校を作るべきだというようなことを様々議論してきて、それが労働組合に一番多く関わる内容でした。そのうち、教育全般についても組合の活動の中でいろいろと議論研究をしてきて、そこから深く関わるようになってきました。
佐藤書記長:私がこの職に就いたきっかけは、大学院時代の教授からの声かけです。大学院を卒業後、まだどのような社会人人生を歩むか全然考えられていない時に、当時の教授から「フラフラするなら神奈川で臨時的任用職員を探しているから働いてみないか」と誘われ、教員として働き始めることとなりました。一番最初の初任校で5年間勤務をし、その後、神高教の執行部に来て、現在5年目を迎えます。
神高教で働くことになったきっかけについてですが、私自身、元々は絶対に学校を働きたいという意向ではなかったため、委員長に声をかけてもらい、視野が広がるかもしれないと感じ、役員を引き受けました。組合自体には臨時的任用職員の時から加入していたのですが、最初の配属先の学校には組合員がたくさんいて、加入を勧めてもらいました。そこでは「お寿司の会」というイベントを月に1〜2回開催したり、学期末にみんなで食事をしたりなど、とても雰囲気が良かったことを覚えています。
そういったイベントに参加する中で、労働組合や加入している方々の温かさや労働組合の存在感を感じており、加入することになったという経緯です。あとは、大学院の社会人経験の同期が「社会人になったら労働組合に入るもんだよ」って、教えてくれていたこともあり、組合加入にあたってのハードルはほとんどなかったですね。
注力されている業務
佐藤委員長:委員長として、全体をまとめるということはありますが、基本的には書記長がメインで業務をまとめてくれています。強いて言えば、渉外や全国での集まりに参加したり、県内の労働組合の横のつながりで会議体を運営していたりなど、外部との関わりがほとんどですね。
神高教内での担当っていう意味でいうと、レクリエーションの釣り大会を運営しているくらいですね(笑)。元々釣り大会はずっと担当でやっていた事もあり、中ではそういったイベントやレクを実施しています。
佐藤書記長:書記長の仕事をここでバシッと説明したいところは山々なのですが、実は、書記長になってから10日目なので何とも言えない感じですね(笑)。昨年度まで、本格的に担当となったのは2022年からですが、執行委員として2020年から4年間、組織拡大に向けた取り組みを行ってきました。そのため、そもそも書記長はどんな仕事なのかを今まさに探ってるところです。
ただ、今後やっていくメイン業務としては、県内の労働条件等を教育委員会と擦り合わせたり、交渉したりすることがメインの仕事になっていくと思います。その他、結構細かいことではありますが、ちょうど2,3日前に健康診断の項目変更があった際の問い合わせ対応をしたり、不合理なルールを何とか変えたりなど、細かい日常業務の対応もやっていたりします。
神奈川県高等学校教職員組合様の現状や課題について
佐藤委員長:教職員の多忙化は非常に課題だと感じています。忙しいこと自体も問題であると思いますが、忙しいがゆえに、労働組合に関わる時間も年々減ってきているんですよね。我々が行う会議に参加することも難しかったりとか、資料を提示しても読み込んでもらえなかったり、ある意味では、労働組合にとっての忙しさというのは非常に阻害要因な面があると考えています。
かつては、組合の中でも自主的な研究組織が数多く存在していたんですよね。土日だけじゃなくて、平日の夕方にも自主的な活動が活発に行われていました。しかし現在は活動の実施自体がなかなか厳しく、数も減ってしまっていると思います。そういう意味で組合活動の活性化の阻害要因の一つとして、多忙化が大きな影響を与えているので、非常に危機感を感じています。
学校の中でのお茶飲み話って、実は、無駄なようで非常に役立つんですよね。放課後にお茶を飲みながら、「あの生徒がこんなこと言ったよ」とか「あんなことあったんだよ」っていうのが、意外と生徒への対応のヒントになっていることって結構あるんですよね。
だからこそ、そういった何気ない会話をする余裕が学校にもなくなってきているので、必然的にやらなきゃいけないことをやってすれ違っているという側面が非常に大きいんじゃないかなと思っています。よく学校もね、昔は喫煙室で物事が決まるってことがあったりしましたね。普段接点のない人と、そこで会話をする事も結構あるなかで、たばこを吸う必要はないと思いますが、そういうバズセッションというか、インフォーマルな接点というのは、実は大事なんじゃないかなと感じていますね。
佐藤書記長:組合に入ることが当たり前じゃなくなってきている層が定着をしていることが、本当にこれでいいのか?と感じるようになってきました。特に、私たちは、任意団体で極論組合に入らなくてもいいし、結局区別できないので同じ権利が与えられるんですよね。
ただ、そうなるともちろん交渉力は弱体化して今あるものを維持することすら危うくなってしまうのは明らかです。「自分は労働組合に入っていないんだけど、組合員と同じ権利を持ってしまっているな」と、後ろめたさを感じてくれればまだいいのですが、「組合員に感謝でーす」みたいな人たちが出てきてる感じがあって、そこが今一番しんどいです。
どうしてもメリット論になるというか、毎月組合日を払ったはいいけど、それに見合わないから辞めてしまったり、加入しないみたいな、意見も出てくるようになっているので、このメリット論になってしまうことも課題感を感じていています。
佐藤委員長:僕らの世代は、ある意味加入することが当たり前と捉えている層が比較的多かったと思うんですよね。最近だと、「生徒に対して、生徒会に入らないという子がいたらどう説得するんだろうか」って考えたりするんですね。あるいは、「PTAに入りたくないって親に対して、教員という立場からすると、いやいや入ってくださいよ」と、恐らく伝えたくなると思うんですよね。
そこで、僕の話し方だと、「例えば、部活の予算に生徒徒会費が使われていたり、PTAの行事に出席をして、その予算が使えるなど、自分に還元されていると感じない人にとっても、実は、その立場を代表する組織があって、その意見を集約して、誰かに渡せるというのは、一つの意義になるんじゃないんですか?」と、説得はするんだけれども、なかなか理解されない事も多くありまして。そういう意味では、公共的な役割に対する意識が欠如してきていると言い過ぎかもしれませんが、そんな一面もあるかなと思っています。
私は、経済学が好きなので、経済学用語で例えると、「合成の誤謬」ってよく言うんですよね。「一人一人の合理的な判断が良くない結果をもたらす」という意味になります。例えばで言うと、「個人にとって数千円の組合費を払わない」というのはある意味合理的なんですね。
ただ、全員がそういう対応を取ると、どうなるかというと、「自分たちの給料を上げるという交渉体がなくなるので、そのことによって、結果的に全体の給与水準は下がってしまう。」というように、合理的な判断の集合が必ずしも合理的な結果を生むとは限らないと思っています。
現状に対しての打ち手やお取り組み、大事にされていること
佐藤委員長:大事にしていることでいくと、ひとりひとりの組合員と役員との接点を持つようにすることは意識していますね。新採用の人には、全員に会おうと思って、現場に出向いて、会うようにしているんですよ。物理的に難しい場合は、お手紙を使ったりというようなことも含めて、なるべくこちら側の情報発信を繋げられるように意識しているところですね。
もう一方で、どうしても、各学校にいる分会の役員に負担感をかけてしまうことですね。相対的に、「負担に対してメリットは?」という風な問いだけではなく、「組合に入るとやること増えるんでしょう?」と抵抗感に繋がる部分もあるので、なるべく抵抗感持たれないように工夫しています。役員にはなるべく負担感をかけないで、活動の領域自体も見直していきながら進めていくことは非常に意識しています。
佐藤書記長:加えて、「基本的にできることややれることは何でもやろうよ」くらいのスタンスで何かできる案がないかっていうことを考えながらも、まずはやってみて、やりながらまた考えていけばいいんじゃないかと思っています。
この間、配る紙の数を明確に減らし、TUNAGの使い方も少しずつ変え始めました。具体的には、TUNAG自体がSNS感覚で使えるようにスタッフブログというコンテンツを立ち上げました。まずは組合本部のメンバーについてや組合本部の何気ない日常を見てほしいなという思いで、週1回のリレー形式で回していく取り組みを始めました。
ちょうど前回投稿してもらったのは、「事務所付近にある公園の桜が大嵐で散ってしまった」みたいな様子など、本当に何気ない日常を投稿することから親近感を持ってもらえるように始めています。投稿のハードルも下がりますしね。今までは公式からの一方通行で、フォーマルな発信しかできていなかったので、身辺雑記を交えていきながら、投稿者側の敷居も下げて実施することが目的の一つです。
結果的にですが、登録者も飛躍的に増えました。こういった投稿を始めてから、約700人程度増えたので、如実に数字にも現れたことがよかったですし、シンプルに嬉しかったですね。
組合員とのコミュニケーションや関係構築で大事にされていること
佐藤書記長:日頃から、負担感を抱えながら、組合活動や業務をやってくれてるので、とにかく基本ですが、レスポンスを早くすることは大事にしていますね。あとは本当に親身に話をする、誠実に対応するというただただオーソドックスなことを大事にしています。特別新しいことはやっていません。また、一般的な労働組合だと、本部があって、支部があって、分会がある組織編成になると思いますが、我々は、本部があって、直で分会があります。
ですので、組合員全員が対象です。なかなか一人一人の声を聞くことが難しかったのですが、TUNAGの導入で常に個人からダイレクトに相談が来るようになりました。大変ではありつつも、リアルな現場のお悩みとかを集約できること自体は非常にいいですね。
佐藤委員長:我々の強みは、支部がないので、現場との距離感が近いことが強みの一つでもありますね。執行部は、年間3〜4回ほど、それぞれの学校を回っています。職場に行っても、本部の人間が来るということはあまり珍しくはないのですが、他の日教組の組合からは、「そんなに回っているんですね!」と驚かれるくらいです。
だからこそ、執行部のメンバーを組合員の皆さんが覚えてくれているので、顔見知りであったり、一度会ったことのある人だと話しやすい事もあり、毎日相談の連絡がきたりすることにも影響していると感じています。
佐藤書記長:余談ではあるのですが、他の執行部と比べて、我々の執行部の特徴って、委員長含めて、関係が非常にフラットなんですよね。まず委員長室がないんです(笑)。 普段から雑談も飛び交っていて、些細な相談でもしやすい雰囲気で、そこがうちのもいいところだなと思っています。
次期役員の育成や輩出について
佐藤委員長:先程お伝えしたように、かつては色々な活動があったので、そういった活動の中で、目立っている方や率先してリードしてくれている方に、声をかけていましたが、現状だと、活動の実施自体もですし、次期役員候補が年々減ってきていることが一番大きな課題かなと感じています。
だから、オンラインも含めて、ラフな意見交換ができる状況なり、コミュニティーを作れるかというところが、新しく担い手を探っていく上では、大きい要素なんだろうなと思っています。若いメンバーのコミュニティを作りたい思いもありますね。我々には、青年部が無いので、それに変わるような取り組みを動かしたいなって思ってます。
労働組合の未来
理想の組織像や目指していきたい姿について
佐藤委員長:「労働組合は、社会全体に必要なんだ」という打ち出しをもっとできればいいなと思っています。いわゆるインフラなんだと。「労働組合がなければ、労働環境や職場環境を改善したり、維持したりできないよ」というのをもっと分かりやすく打ち出したいなと思っているところです。そのためにどうメディアを活用していけばいいか、それが我々にできるのかどうか、議論をしていきたいと思っています。
我々、日教組全体の中で、高校の組織というのは、規模が縮小傾向にありますし、高齢者が多い部分もありますので、新しいアイデアが出てこない点もあるので、他業種を含めて、組合の意義をどう広められているのかについて、意見交換等を通して、学んでいきたいなと思っています。ですので、組合の意義付けを明確にし、皆さんにわかりやすいものを作っていきたいなと思っています。
もう一つは、昔から積み上げてきた歴史をおさらいする作業をやってみたいなと思っています。休暇や給与、手当といった分かりやすいものから、職場環境や労働条件等、さまざま獲得してきたものがあるからこその今があると思うので、歴史的にどう掴み取ってきたのかを今後後世に伝えていくためにも、まとめていきたいなと思っています。
それこそ、年配の女性組合員のOGだと産休すらなかったんですよね。子どもを産むと、仕事を辞めるか、親に預けるか、の二択しか無い世界だったわけで、そこから考えれば、今はだいぶ整備されてきているわけですし、まだまだ改善の余地は大いにあると思いますが、こういった獲得してきた歴史を少しでも若い世代に知ってほしいなと思っています。
佐藤書記長:やっぱり、若い人達を大事にしたいんです。20代30代が、組合ってものが当たり前だよという存在になっていってほしいし、その若い世代の人達が自分たちで組合の存在を当たり前にしていくんだと、作っていってほしいですね。ここが今後の神高教の歴史にも大きく関わってくるのかなと思っています。
一方で、長い歴史の中で色々獲得してくださった先輩方がいますが、先人達の歴史を大事にしながらも、古いやり方が合わない部分もあると思っているので、現代に合うやり方も模索していきながら、バランスを大事に今後に残していくための活動をできればと思っています。
だからこそ、紙の配布に追われることが役員の仕事かと言ったら、そうじゃないとおもうんですよ。その時間を校長との交渉の時間にしたり、組合員の相談を聞く時間を設けるであったり、そういったコアな業務に注力するべきだと思うので、少しずつでもいいので、若い人達の声は大事にしながら、組合活動の在り方を変えていきたいなと思っています。
〜佐藤(治)委員長、佐藤(彩香)書記長、ありがとうございました!〜







-300x225.jpg)




