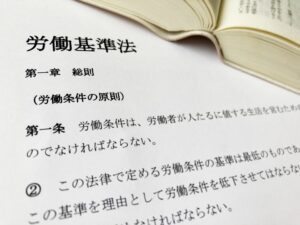労働組合の労働者供給事業とは?労働市場における組合の役割を解説

労働者供給事業は、労働組合が組合員の雇用促進と労働条件の改善を図る上で重要な事業です。労働者を企業に供給する点で労働者派遣業と似ていますが、雇用関係や指揮命令系統、利益の分配方法などに違いがあります。労働者供給事業の基本を理解しましょう。
労働者供給事業とは
労働者供給事業は法律で規定された厚生労働省の認可事業です。まずは、事業の概要や労働者派遣業との違い、主な事例について解説します。
労働者供給事業の意味と定義
労働者供給事業とは、主に労働組合が供給元となり、企業へ組合員(労働者)を供給する事業です。職業安定法第45条に基づいて行われます。
労働者供給事業は原則として職業安定法により禁止されていますが、労働組合などに限って例外的に認められているものです。
労働者供給事業を行っている労働組合は供給先企業と労働協約を締結し、企業と組合員が労働協約に基づいて雇用契約を結びます。賃金は企業から労働者に直接支払われます。
労働者の権利保護や労働条件の改善につながりやすいことが、労働者供給事業における労働者側のメリットです。また、企業側も特定の分野に特化した専門性の高い労働力を確保しやすくなります。
労働者派遣業との違い
労働者派遣業は、労働者派遣法により例外的に認められているものです。職業安定法では労働者の派遣を禁止していますが、実際には多くの産業で派遣が行われている実情を鑑み、労働者の保護を建前として1986年に労働者派遣法が施行されています。
労働者供給事業では労働者と供給先企業が雇用契約を結ぶのに対し、労働者派遣業で労働者が雇用契約を結ぶ相手は派遣元企業です。賃金も労働者供給事業では労働者に直接支払われますが、労働者派遣業では派遣元企業に支払われます。
また、営利目的で行われる労働者派遣業と異なり、労働者供給事業は営利を目的として行うことができません。
出典:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | e-Gov 法令検索
労働者供給事業の現状
労働者供給事業の実施組合数は増加傾向にあります。2012年度の実施組合数が86であったのに対し、2021年度の実施組合数は104です。
しかし、実施組合数が増えているのにもかかわらず、実際の供給人数は減少しています。近年で供給人数が最も多かった2013年度の34,745人から、2021年度には15,080人にまで減っています。
一方、労働者派遣業で派遣された労働者数は労働者供給事業の数十倍にのぼっており、労働者供給事業の優位性が生かされていないのが実情です。
労働者供給事業の主な事例
労働者供給事業における供給実績が最も多いのが、自動車運転職の供給です。清掃車運転者・生コン運転者・一般トラック運転者などを供給しています。
自動車運転職に次いで供給実績が多いのが、港湾などで働く運搬労務職です。自動車運転と運搬労務は、労働者供給事業における2大職種といえます。
これらの職種以外にも、訪問介護やシステムエンジニア・プログラマー、旅行業添乗員といった職種で一定の供給が行われています。
労働者供給事業を活性化させるポイント
労働者供給事業にはさまざまなメリットがありながら、労働者派遣業ほどの広がりを見せていないのが実情です。労働者供給事業を活性化させるためのポイントを解説します。
非正規労働者の組織化を図る
日本の労働組合は企業別組合がメインであり、企業別組合は正社員を中心に構成されています。しかし、現在は就業者の約4割を非正規労働者が占めているため、労働者供給事業を活性化させるためには非正規労働者の組織化を図ることが重要です。
非正規労働者が加入しやすい体制を整えた上で、正社員と非正規労働者の利害調整を行う必要があります。
事業組織として営業機能を強化する
労働者供給事業が労働者派遣業に対抗するためには、労働者供給事業を組合活動の片手間に行うのではなく、事業組織として営業機能を強化することも大切です。
ただでさえ忙しい組合活動から労働者供給事業を分離させるのは難しい側面もありますが、リソースを確保できなくても、検討する価値はあるでしょう。
企業側に労働者供給事業のメリットを伝えるには
労働者供給事業を活性化させるためには、提携先企業を増やすことが不可欠です。ただし、実際には質の高い労使関係を築こうとしない経営者も一定数存在します。
労働者供給事業のメリットを根気よく企業側に伝えながら、労使の協働により健全な労働市場を創出することが重要です。採用コストがほとんどかからないなどのメリットを提示すれば、企業側も興味を示してくれるでしょう。
労働者供給事業について理解を深めよう
労働者供給事業では中間マージン分を賃金に上乗せできるため、労働者の賃金改善につながります。ただし、現在は労働者派遣業の勢いが強く、労働者供給事業の優位性を発揮しにくいのが実情です。
労働者供給事業について理解を深め、組合として何ができるか、具体的な取り組みを考える際の参考にしましょう。