【日本中央競馬関東労働組合】日本中央競馬関東労働組合のリアル 〜組合員の無関心を『TUNAG』で変える挑戦〜

現在、茨城県の美浦トレーニングセンターを中心に約1000名の組合員が活動している日本中央競馬関東労働組合。今回は執行委員の斉藤様に、組合員の無関心という課題への取り組みや、情報共有ツール「TUNAG」の導入効果、そして労働組合が目指す未来について詳しくお話を伺いました!
日本中央競馬関東労働組合の組織概要と業務内容
ー最初に組織概要をお伺いできればと思います。事業内容や組合員数、組織体制、支部や拠点の有無など、ざっくりとしたところで構いません。
斉藤:組合員数は約1000人、支部はなく、会社の所在地そのままの拠点一か所で活動しています。我々厩舎スタッフの雇用形態はかなり特殊で、競馬の主催者である「JRA」が雇用主ではなく、JRAから免許を付与され厩舎(事業所)を開業している調教師が厩舎スタッフの雇用主という形になっています。2025年現在美浦トレーニングセンターでは、94人の調教師が開業していて、そのどこかに属し業務を行っています。
その昔、1957年(S32年)に初めて労働組合が結成され労使交渉をやるとなった時に、交渉相手の雇用主は誰なんだという話になり、JRAも調教師も自分達ではないと主張した結果、国会の場で議論され、調教師が厩舎スタッフの雇用主と決まったという過去があります。
まだ最近の話ですが、この主催者が雇用主ではないという構図は、2001年大分県中津競馬場が廃止される時に大きな騒動に発展しました。中津競馬は、売上が好調な時は中津市に売上を繰入れしてきたのに、赤字が続いたら中津市は、手の平を返して廃止に突き進みました。当時の中津市長が「直接の雇用に関係のない競馬関係者に補償金を支払う義務も責任もない」と競馬場廃止に対して補償をしない事を表明。中津市からのこの仕打ちに中津競馬関係者は補償を勝ち取るという目標の元に団結し闘ったという事がありました。すみません、少し脱線しました。
―普段、組合員の皆様はどういった業務をされていますか?
斉藤:普段は茨城県の美浦トレーニングセンターにほぼいます。ただし、週末に競馬があると各地の競馬場に出向きます。また、北海道開催や小倉開催では長期の出張になり最大で約3か月現地に滞在することもあります。
―実際に馬の飼育や世話も皆さんが担当されていますか?
斉藤:はい。基本的に馬の世話をして、調教をつけたり競馬に帯同したりしています。勤務地が美浦でも出張先でも仕事内容は同じです。
―次に斎藤様の自己紹介をお伺いします。組合加入のきっかけや役割までの経歴と、現在の役割・注力している業務内容を教えてください。
斉藤:組合に入ったのは同僚に誘われてイベントを手伝ったのがきっかけです。その後、イベント企画・運営を10年以上担当してきましたが、数年前に執行部に誘われて執行委員になりました。今もイベント企画・運営をメインに担当し、「TUNAG」の管理もしています。
組合員の無関心とその背景にある課題
―現在、労働組合が抱えている課題や困りごとを教えてください。
斉藤:最大の課題は無関心の組合員がいる事です。組合が何をしているか分からず、「面倒くさそう」というネガティブなイメージを持たれているのが課題です。更に最近は、組合に入らない若手が徐々に出始めています。
―組合への関心が薄れてしまった原因は何でしょう?
斉藤:JRAは1997年の売上をピークに、その後は2011年まで14年連続で売上が下がり続け、何も上がらない時代が長く続きました。上がらないだけではなく、現行の基本給より少ない給与体系者の導入、ボーナスの減額、人員の削減、馬房の削減、いくつかの地方競馬の消滅など、とにかくマイナスな事が続きました。春闘でも使用者の減額提示に「下げるな」という交渉が続いた時代でした。「何も上がらない」からの組合への「期待の希薄」そして組合活動への「関心の希薄」に繋がっていったと思います。
新人厩舎スタッフへの説明会を仕組み化し、組合理解を促進する
―組合活動で今後やりたいことや改善したいことはありますか?
斉藤:新人厩舎スタッフに組合を含む各種団体が集まって説明会を開きたいと思っています。多くの企業で、新入社員に対して研修や説明会を実施されていると思いますが、我々の職場では行われていません。美浦トレセンでの仕事と生活、そして各競馬場へ移動しての開催業務を行う、という流れ中でいくつかの団体がそれぞれ重要な業務に従事している。しかし団体の存在は知っていてもどんな業務に従事しているか知らない厩舎スタッフも多く、知らないまま定年を迎える人も少なくありません。
我々は、JRAを中心に先人達が試行錯誤をして作り上げたシステムの中で仕事をして生活を送れている。それらに対しての「無関心」をなくすために、まずは「知ることから始める」。そのためにも、新人厩舎スタッフに対して我々が「伝えられる場」説明会を仕組み化できれば良いと思っています。
TUNAG導入による効果と組合活動の変化
―TUNAG導入後の効果と変化について教えてください。
斉藤:まず「TUNAG」の導入のきっかけになったのが、2023年にストライキが行われた時です。この時は、組合員への情報伝達手段が紙でしかなく大混乱を引き起こしてしまった事から組合員に情報を直接届けるという事が最重要課題となりました。その時に出会ったのが「TUNAG」です。「TUNAG」の良い点の1つに、情報発信に対しての既読数、その既読数に達するまでの時間がわかる事です。これまでは、情宣(紙)を発行しても、どの程度の人が見てくれているのか更にその「興味・関心」の度合が非常に不透明でした。
導入きっかけとなったストの翌年、2024年ストライキの時は既読数から組合員の興味・関心の度合が非常に高いことが読み取れました。また、ディズニーツアーや劇団四季の観劇ツアーなど興味のあるイベントには積極的に参加してくれる傾向があり、情報を見てくれていて興味のあることにはアクション起こしてくれることがわかりました。特に心から嬉しかったのは、「あの投稿、役に立ったよ」と声をかけてもらえた時です。
役員不足を解消し、活動を楽しめる組織づくりを
―今後、どのような組織にしていきたいと考えていますか?
斉藤:役員がもっと増えてほしいです。役員をやる人が少なくなっており、今後の活動を考えると役員不足は深刻な課題です。役員の仕事は大変なことも多いですが、組合員の生活を支える大切な仕事でもあります。イベント企画や運営なども含め、役員活動を楽しんでできる環境を作りたいと考えています。
―最後に、今後期待することはありますか?
斉藤:「TUNAG」が業務の一部として定着し、日常的に情報発信が行われ、組合活動だけでなく他の団体も巻き込んで、業界全体の情報共有ツールとして機能するようになれば理想的です。
〜斉藤様、ありがとうございました!〜



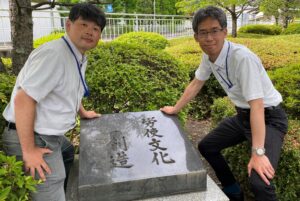






-300x206.png)

