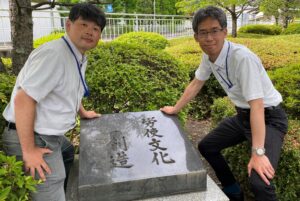【ジェーシービー従業員組合】全国3,800人の組合員が自由にやりたいことをやっていけるような雰囲気を作り、新しい時代に向けた取り組みを体現する。
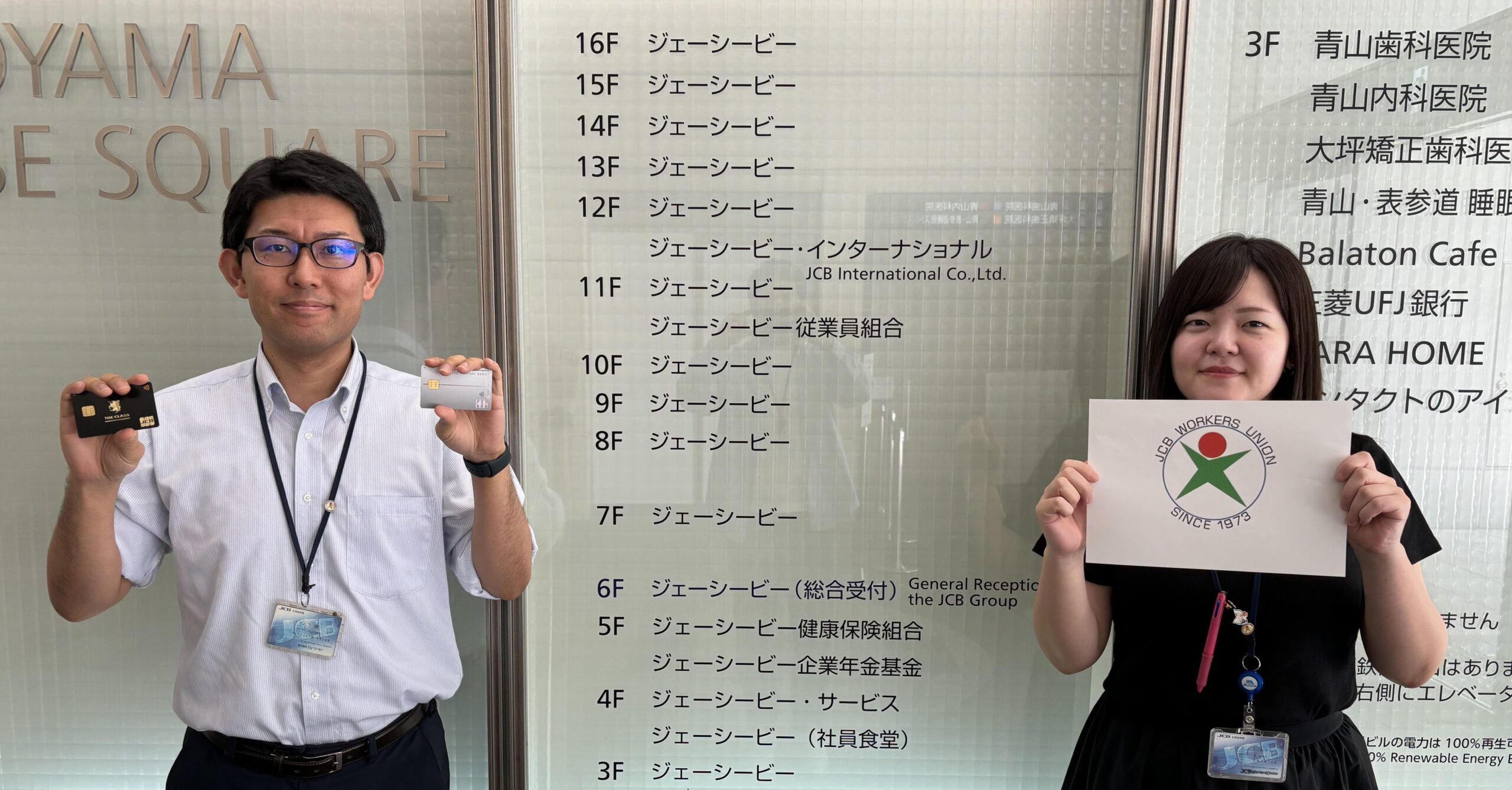
クレジットカード会社である、株式会社ジェーシービーの企業内労働組合であり、約3,800名の組合員を抱えているジェーシービー従業員組合の中央執行委員長の斉藤様(写真左)と書記長の藤川様(写真右)に、労働組合の未来についてお話をお伺いしました!(以下、敬称略)
組織概要と自己紹介
組織概要
斉藤:弊組はクレジットカード会社である株式会社ジェーシービーの企業内労働組合であり、現在組合員が約3800名で男女比でいうと女性が多い組織になっています。また、弊社には時給制の契約社員が全国に約1100名います。その中でも、期限を区切った有期雇用契約社員と正社員と同様期限を区切らずに働いている無期雇用契約社員がおり、そのうち無期雇用契約社員が2016年から組合員化しています。この無期雇用契約社員が徐々に増え、現在では組合員の内2割ぐらいが時給制の無期雇用契約社員になっています。これが弊組のちょっとした特徴です。
組合に関わるきっかけや経緯
斉藤:2007年に新卒で入社後、法人営業の部署に所属し、主に法人向けクレジットカードやETC・タクシーチケットなどの自社商品を大企業に向けて営業していました。その後僅か1年で部署異動となり、入社2年目の2008年6月から2018年までの10年間は、システムの部署に所属していました。クレジットカードの会員様や加盟店様・売り上げなどを管理する弊社の基幹システムを担当したり、社内のイントラやパソコン・ファイルサーバーなどのシステムを担当したりするなど、10年間で様々なシステムを担当していました。
このシステムの部署に所属中、同期の男性から「社内で有志勉強会をやろう」と声をかけてもらい、同期や先輩・後輩など約10人の男性が集まる有志勉強会に顔を出すようになりました。その当時、社内提案制度が始まった直後だったので勉強会メンバーで「新しいサービスや新規ビジネスを考えて提案してみよう」という流れになり勉強会を行っていたのですが、その中の1人の先輩が組合の執行委員をやっていたんです。
当時システムの部署は、東京の赤坂に拠点があったので「赤坂支部の組合メンバーにならないか」と先輩に誘っていただき、執行委員になりました。その後時を経て「赤坂の支部長をやらないか」という話をいただき、赤坂の支部長をやらせていただくことになりました。更に、赤坂にあったシステム本部が高田馬場オフィスに移転した際に支部長をやっていたので、高田馬場支部の立ち上げもやらせていただきました。
そして2018年、組合の中での役員歴が積み上がってきたころに組合の中心メンバーである四役(委員長・副委員長・書記長・副書記長)に加わらないかという話をいただき、これと同時に会社の業務から離れて専従者になりました。私自身、入社2年目からシステムの部署にいたため、社内の様々な部署のことをよく知らなかったというのが正直なところです。専従者になるといろんな拠点に顔を出して職場のことを聞き、課題も目にするようになるため、会社のことをよく知る機会になり自分にとってもプラスになるだろうという想いもあり、専従者になることを引き受けました。
専従者になった直後には、委員長も務めることになりました。その後2020年からコロナウイルスが流行し、組合の活動にも色々な制約が出てきましたが、「TUNAG」があることで新しい活動方法の検討・実践を進めることが出来ました。例えば、代議員大会の審議はペーパーレス・オンライン化を果たし、組合員の自主的な企画で行うオンラインイベントへの補助制度などもできました。
藤川:北海道生まれ北海道育ちで2012年に新卒で北海道支社に入社し7年半、コールセンターの部署で業務を行いました。その後、部署異動となり債権を回収する部署で3年半業務を行いました。そして、2024年4月に業務から離れて北海道から東京に移り、専従者になりました。
私は、入社して2年目の時に北海道支部の執行部に入りました。先輩や同期に声を掛けてもらい、これまでの組合活動やイベントに参加した中で「みんな楽しそうだな」「自分のいる部署以外の人とも関わりを持てるかも」と思ったのがきっかけでした。
組合に入った後は、何年か北海道支部の支部メンバー・副支部長を務め、社内の様々な相談を受ける「なんでも相談窓口」という活動にも参加しました。その後、北海道支部の支部長やなんでも相談窓口のリーダー、副書記長を務めました。「副書記長にならないか」という話をいただいた時は少し迷いましたが「自分の心が動いてわくわくする方に行った方がいいと思うよ」と周りに言っていただいたこともあり、引き受けることにしました。
そして、2023年10月から書記長を務めています。当初は、通常業務と兼任して非専従でしたが、斉藤さんから「組合は、どのような職群だろうが、どこに住んでいようが、どのような人でも活躍できる場なんだよ」「組合であればどんなことでもできるんだよ」という思いを聞いて自分自身もそれに共感できたので北海道から東京に転勤して専従者になることを決めました。
現在、注力されている業務
斉藤:まず内部的なところでは、主に会社との窓口を担っています。例えば、交渉事や組合も共に考えてほしいと会社から持ち込まれる課題を最初に着信します。また、組合の組織運営の責任も持っています。全国の拠点にある8支部それぞれの動き、拠点に限らず人事制度や賃金などの横断的な課題に取り組む本部の動きをウォッチしています。
次に外部的なところでは、ジェーシービー従業員組合の代表者として様々な他労組の方との打ち合わせや情報交換に藤川と二人で出向いています。また、同業他社であるクレジット産業の労働組合が集まる会議体(クレ労)があり、持ち回りで幹事をやるようになっています。2年ごとに概ね3〜4つの組合が幹事労組をやって運営していくのですが、まさに今期が幹事労組になっているので、このようなクレ労全般の運営や他の幹事労組との連携を行っています。
ジェーシービー従業員組合様の現状の課題
斉藤:まずコロナウイルスが流行する以前からジェーシービー従業員組合というのは大きく2つの役割を組合員に認知されていたと思っています。
一つは、意見を集めて組合の中で議論をして会社と協議をしていくという従業員代表の役割です。コロナ前は、座談会や職場集会と称して昼休みに会議室に集合し、ランチを食べながら組合の持ちこんだテーマに対して意見を出してもらったり、現状会社が考えていることに対して意見を求めたりなど意見交換を対面集合でやっていましたがこれがコロナ禍ではできなくなりました。
もう一つは、イベント開催の役割です。8支部それぞれがオリジナルティーを持ってイベントを行ってくれていましたが、コロナ禍では対面集合ができなくなったためこのようなイベントは軒並みできなくなりました。特にイベントの中で言うと、各拠点で伝統として毎年開催していたクリスマスパーティーもコロナによってできなくなりました。ホテルの宴会場を借り立食パーティーの形式で拠点ならではのプログラムを行う、組合のある意味シンボルのようなイベントだったんです。
コロナによって今まで組合がやっていたことを否定する世の中の動きになってしまい、私の委員長の任期中の半分以上はこのような状況に置かれたということがここ最近の動きです。またその間に、各支部にいる組合の活動を支えてくれていた執行委員の中堅層がかなり辞めてしまったんです。
そのため執行委員の年齢がかなり若返ってしまっています。現在全国で100人くらいいますが、7~8割ぐらいがコロナ禍以降に入社した若手メンバーになっているんです。結果的に、イベントや組合員との意見収集に参加者として体験したことがないメンバーが集まっているというのが現状です。
実態に対しての現状や取り組んでいる事、打ち手
斉藤:弊組は、10月始まりの1年間で1期になるのですが、去年の10月からの重点活動においては、支部活動の活性化というところで支部活動を元に戻すのではなく、新しい方法も取り入れながら新しい時代に向けた取り組みを体現しています。
もう一つは、座談会です。ちょうど1年前ぐらいから対面で話したり、マスクを取ったりすることは許されるようになってきましたが、今一度各現場で意見収集をするというスタイルを復活させられるように今期は目指しています。ちょうど4月から藤川が専従者に加わってくれたので、さらに拠点に出向いて意見収集を行っていきたいと思っています。
またそれに加えて若手には、座談会がどのようなものなのかということを実際に参加して知ってもらいたいですし、その中で職場にいる色んな組合員の人の声に直接触れることも大事にしてもらいたいと思っています。そうすれば、幾ら若くても経験がなくても物怖じせずに触れ合ってもらえれば、現在の組合の裾野の下にいる者達が5年10年と力をつけてこのまま執行委員を担うことで、むしろパワーアップできるのではないかと思っています。
各支部ごとの取り組み
斉藤:各支部はそれぞれで支部計画というものを期初に作ります。そこでイベントの予定等も立てていきます。更にそこに予算を付けて基本的には支部活動は、支部の自治のもとで展開されます。ただ、会社との調整をしなければならないような施策も中にはありますし、場合によっては他の拠点と一緒にやった方がいいものもあったり、支部の担い手も年によっては新しい担い手に変わったばかりの年があったりするので、その場合は専従者がフォローしながら活動計画を一つ一つ形にしていっています。私も藤川も支部長の経験があるため、支部の運営をフォローしています。
先ほどお話に出したクリスマスパーティーについては、各拠点と言いながらも東京は3つ支部があったため、東京の3つの支部が合同でクリスマスパーティーをやっており、支部横断で行っているイベントもありました。ただ、基本は各支部の自治なので、様々な場面で支部を越えて行うことはあまりなかったです。
各支部がオリジナリティーを持って行ってもらうというのが基本でした。ただ、そればかりだと結局その拠点でしかできないことやその拠点で経験しているイベントなどが繰り返し行われることになりつつありました。そうなるとやはり、新しい方法や新しい内容の施策も行って、より活性化させていきたいという全体の動きからすると、厳しい言い方にはなりますが、ただ単に昔に戻っているだけでは駄目だと思っています。
なので、もう少し本部主導で拠点を越えて組合員が繋がれる仕組み、施策を今期は行っていきたいと思っています。更に、弊社の北海道支社が再来年にオフィス移転をする予定があるのですが、北海道支社は、実は昔は別の会社だったという独自の歴史を持った拠点です。当時の別会社だった時に入社した組合員もいますし、総合職として転勤で北海道支社を経験した組合員も全国にいます。
この支社移転を契機に、北海道というところを共通項に組合員を繋ぐようなイベントや取り組みを今期から仕掛けていこうということを現在準備中です。支部活動の活性化に向け、方法が次の支部活動で応用されればいいなと思っており、今回の取り組み自体は本部主導で各支部巻き込んでやっていこうと思っています。
意見収集や支部活動において大事にしていること
藤川:私が大事にしているのは、組合員を全体として捉えることです。組合員には様々な属性の方や様々な環境の方がいます。何か議論をしたり何かイベントを行ったりする時に、それぞれの職群の方の考慮はできているのかとか議論の場でどう思うのだろうかということを常に考えるようにして、周囲にも投げかけています。
斉藤:藤川の話と重なるところもあるかもしれませんが、組合員はやはり属性も境遇も多様になってきています。一方で、全国に100名いる組合の担い手である執行委員のメンバーはほとんどが若手になっていて、人事制度における昇格を年次的にも経験したことがない者が多いわけです。そうなると、人事制度とか様々な職群の人たちとか、拠点のあの人たちとか、自分とは違う境遇や属性の人たちの話題が出た時に自分ごとで語るのがなかなか難しいと思います。
これは、先程も触れたように座談会などの対話の中で色んな人と触れ合うことで経験値を積んでもらえばいいと思っていますが、何かイベントをやるとか声を聞きに行こうという時にどうしても自分たちの物差しで内容を作り始めてしまうんです。
そうなった時には、コロナ前も含めて長年組合の活動に従事してきた私が、色んな観点を差し込まなければいけないと思っています。またそれと同時に、その担い手である彼らも多様性の中のひとりなんだというところもあるため、無下に否定してはいけないとも思っています。非常に難しいところではありますが、自分とは異なる境遇の人たちをも受容しなければいけないとか、存在自体を認識しなければいけないみたいなところを伝えていくことは、イベントの企画でも議論でも様々な意見交換の端々で意識しています。
未来への想いやありたい姿とは
斉藤:新しいことを体現していきたいという話をしてきましたが、この背景には、全国にいる3,800人の組合員がより自由にやりたいことをやっていけるような雰囲気になってほしいという想いがあります。現状、みんなが無意識のうちに「制約」だと境界線を引いてしまっている状態なのではないかと感じています。
例えば、対話をしよう座談会をやろうと言っても、過去のやり方を知っている人は他の方法を想像しなかったり、過去を知らない人は全く何をやっていいか分からなかったりというような状態になり、それが各々の制約になっています。また、こんなことは相談したらいけないんじゃないかとか、こんな企画は組合でやってはいけないんじゃないかとか、どこかに線を引いてしまっていると思うんです。
執行委員の中でも、このような制約がいくつもうごめいていますが、組合員はもっと狭まった制約を無意識に感じていると思います。今後の色々な取り組みで様々な方法をみんなが見聞きすることで、そこまでやっていいんだとか、こんなやり方ができるんだったらこのやり方もやれるんじゃないかとか、制約の線が緩やかに広がっていくことができるといいなと思っています。
また、結果的に組合というのは一部の執行委員の持ち物ではなく、3,800人の組合員が主体者なので、やりたいことが3000何通り出てきていいと思っています。会社の業務や人事部ではできないみんなの好きとか得意なことを組合というフィールドの中でやれるのが当然というところまで持っていけたらいいなと思います。
藤川:私は、組合ならではの繋がりをもっとみんなに感じてもらいたいと思っています。
斉藤さんとも組合活動に参加しなければ関わることはなかったと思いますし、組合イベントの中で繋がった人や話す人ができたこともありますので、このような組合ならではの繋がりをぜひみんなにも経験してほしいと思っています。
私は、この繋がりがあったからこそ、今いろんな方と話せるようになっていますし、組合に入って良かったと思えているので、このような組合ならではの繋がりを増やす活動をやっていきたいと思っています。そして、会社との交渉などもちろん真面目なところもやっていきますが、もっとみんなが楽しく自由にやっていけることを私からも発信していきたいと思っています。
〜斉藤様、藤川様、ありがとうございました!〜