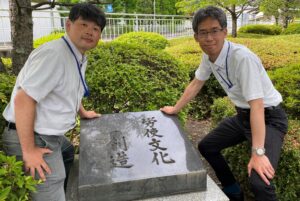【イオンフィナンシャルサービスユニオン】組合活動を定量化し、組合の存在意義と向き合い続けた5年間。書記長として組合と組合員をつなぐことに魂を注ぎ、多くの課題に取り組んだ時間を振り返る。

イオンフィナンシャルサービスユニオンの前中央執行書記長であり、TUNAG for UNIONの初代アンバサダーの佐々木様に、労働組合の業界全体への想いから、組合活動で注力したお取り組みや成果などの組合活動に従事された振り返りを幅広くお伺いさせていただきました。
組合活動に従事された期間の振り返り
佐々木さんの目から見た組合業界全般の問題点・課題
2019年10月から専従として組合の業務に関わるようになりましたが、当時を振り返って最初に感じていた課題は大きく2つです。一つは、労働組合としても業界としても数字がない(定量的に測りにくい)活動だということです。会社の中の営業では、予算があって目標達成に向かうというのが指標になります。これに比べて組合活動は、数字を意識した活動が少ないということを一番最初に感じました。これは、組合の組織の考え方や組合の専従の方の考え方など色々あると思いますが、個人的に思ったのは数字がないと各種活動の振り返りができないということです。例えば、どれだけ良い活動をしたとしても、「あの企画は楽しかったから良かったよね」とか「みんな盛り上がってたから良かったよね」というような振り返りしかできないので、そこの数字を作っていくというのは必要な作業だと思いました。
そして、もう一つが労働組合の存在意義とその周知です。「労働組合ってそもそも何だろう」というのが知られていないことが課題であり、労働組合の存在意義を知ってもらう必要があると感じていました。具体的には、レクリエーションや会議を開催しても大体いつも同じメンバー、似たような顔ぶれになりやすい点が挙げられます。それは経験値が蓄積されるというメリットもあるかと思いますが、労働組合の活動周知、新規参画者を増やすという観点では改善が必要な部分です。この2点が当初感じた課題です。
また、業界特有かもしれないのですが、「年齢層が高く、男性が多い」という傾向もあります。業界として、女性リーダー推進のための会議や参加者を女性限定にした会議を開催しています。しかし、前提として女性の方から見て組合活動が魅力的に見えないとそもそも参加したいと思って頂くことは難しいです。そのため、労働組合の存在意義を丁寧に伝え、魅力を発信していく必要があると思います。それが将来的に女性の参画者を増やす、新たな後任者の発掘などに繋がる助けになります。
「年配」「男性」という2つのキーワードで取り組んだこと
弊組は幸いなことに、執行委員メンバーは半数以上が女性です。執行部体制は現在22名ですが、うち13名が女性のため、他の組合さんとお話をしていても驚かれます。数年前と比較すると、中央執行委員の数も増え、女性比率も上がっています。これをしたから女性が増えたという決定的なものはないのですが、やはり女性に中央執行委員をお願いすることで参加者側も参加しやすくなるということはあると思います。男性しかいないところに来てくださいというのはなかなか大変だと思うので、そこは組織を作るという観点では重要だと思います。
あとは、結果論になってしまうかもしれませんが、それだけ女性が執行役員を快諾頂けているということは組合活動にある程度魅力を感じてくれているのかなと思います。こちらから打診するのは自由ですが、当然受けてもらえないこともあり得る話です。それがまさに組合業界の課題であり、専従の後任が見つからない、役員の後任が見つからない、バトンを渡せないというのがよくある話だと思います。弊組はそういった意味では、バトンを渡そうと思った時にしっかり女性がやってみますと受け取ってくれる環境になっていたのが良かったのかなと思います。
ご在任期間中に特に力を入れた取り組み
TUNAGを入れるか入れないかというところを考えた時に自分の中で思っていたことが2つありました。一つは、先程お伝えしたように組合というものを知ってもらう必要があると感じていたので、「魅力を発信して意義を伝えたい」ということ。もう一つは、「誰が組合活動に関わってくれているのかを知りたい」ということ。この2点がTUNAGを導入するきっかけにもなったところであり、組織運営を考えた時のポイントでした。
1点目に関して言うと、組合の意義・魅力をしっかりと伝えるには、広報や情報発信をするためのツールがないとできません。旧来であれば紙で広報紙を作って定期的に発行していくという方法がありますが、時間や費用がかかり、組合員に届くまでに1〜2カ月かかってしまいます。かつ、誰が読んでいるか分からない、届いているかも分からないというところもあったので既読確認が出来ること、情報鮮度の高いままタイムリーに伝えるツールが必要でした。あとは、TUNAGの機能面の話になりますが、ただ伝えるだけで一方的に情報を流すだけであれば、他のツールでも良かったのですが、会議とかレクリエーションの申し込みのフォームを作れたりアンケートを取ったり、細かい部分も全てをまとめられるというのが一番の強みだなと思いました。
2点目に関して言うと、元々の組合の課題であると思っていた「大体毎回同じメンバーだよね」というのが本当なのかというところを知りたかったです。いつもレクリエーションに来るのはこのメンバーだけど、組合の情報を知りたいとか関わりたいという人は他にもいるはずなので、その人たちを知りたいしその人達にもっと関わってもらえるような取り組みをしたいと思いました。
実際にこれは効果をすごく感じています。レクリエーションとか会議とか組合活動に今まで来たことがなくてもTUNAGは毎週必ず見ている人がかなりの数いることが分かりました。これはTUNAGだから分かったことであり、この5年で組合として新たに発見できたことかなと思います。
ご在任期間中に取り組みきれなかったこと
個人的に悔しい、もうちょっとやりたいところで言うと、TUNAGを導入して多くの方に登録していただいているのですが100%ではないというところです。個人的・組織的にもう少しやりたいと思うところは、未登録者を減らすというところです。今は、月間のログイン率で言うと7割弱ぐらいです。業界水準だと20〜30%のログイン率ということを聞いているので、個人として組織の書記長として絶対にそれを超えるもしくは業界を引っ張る数字を出すというのは意識していました。個人的には、50%をずっと切らないでむしろ8割を目指したいという思いがありました。
組合の情報なので、組合員が自ら意識して情報を取りに来てもらわないとこの数字にいかないので結構ハードルは高いかもしれないですね。そして、ログイン率は比較的高いですが、未登録の方はまだ500名いらっしゃるので、これを段階的に減らしていってより多くの方に組合活動を知ってもらう状態をつくりたいなと思います。

TUNAGについて
TUNAGをご導入頂いた背景
まず、5年前に私が専従になるタイミングで当時の委員長から「組合活動をデジタルシフトしてそれをスマホで全部できるようにしてほしい」というミッションをいただきました。それを考えた時に、先程話したように広報だけをやるのでは意味がないと思ったので、これを入れるからには色々やりたいこと、できることを集約したいと思い、各種業務や運営の棚卸しをしてこれに集約していくイメージで取組みました。
次に、予算の話に関してTUNAGは比較的高いと言われますが、弊組で言うと、例えば年間で紙の発送や広報誌デザイン料、新聞を作る際の構成、印刷会社への支払いなどでかかる料金、北海道から沖縄までの各事業所への発送費用、紙の購入費など今までかかっていた金額は1年間でどれぐらいだろうと計算した時に、大きな金額がかかっていました。そのため、私が執行部の方に提案をした際は、「年間でこれだけの各種手数料、お金がかかっていますが収支でもプラスになります」という説明をしました。単純に今の組合の年間予算の中でいきなり大きな額が追加でかかりますと言ったら「代わりに何を削るんだ、どうするんだ」という話になると思うのですが、そうではなく、「今かかっている費用と同程度であり、さらに出来ることが増えます」というような形で提案をしました。弊組の場合は、収支でも黒字・プラスでした。
執行部の中では、あり方を求める方とロジックを求める方で分かれるんです。「スマホでできたら便利だよね」と便利さで賛同する方もいれば「便利だけどそれだけ高いものは入れたくない」という方もいるので、両方に対応できるような提案をしました。労働組合は、組合費で運営しているのでそこの納得が得られないとどんなに良いものでも高すぎると導入が難しくなります。収支でもプラスでスマホでもできるというところの提案をしたら大きな反対はなく、むしろ「もっと早く入れよう」、「こういう機能もありますか?」など積極的な意見や質問を頂きました。新ツールの導入は組織運営において重要な決断になるため、提案した際は賛成してもらえるか少し不安だったのですが、当時の執行部の皆さまに背中を押してもらえたことが大きかったです。今でも当時の執行部の皆さまには感謝しています。
結果として、活動をスマホでできるようにしたいという目指すべき姿と収支でもプラスになるというこの2点をしっかり伝えたことが導入に繋がったと要因だと思います。
デジタルツールの導入によるご年配の方への不安
ご年配の方が使用出来るのかというご意見はありました。ただ、弊組は会社のサービスとして決済アプリをお客様に提供している会社です。そのため、お客さまへアプリの説明をしているのであれば、今回の組合でのアプリ導入も問題はないというのが執行部の考えでした。
これはご相談を頂く他労組の専従・執行部の方々に伝えているのですが、「年齢層高いから」とか「スマホ苦手な人が多い」というのはちょっときつい言葉かもしれませんが、執行部の決めつけにすぎないと思っています。弊組で言うと、アプリ導入時、年齢層の高い組合員が多い東北エリアが最もTUNAGを見てくれていてログイン率も高かったです。反対に、若い方が多い関東エリアは低い傾向がありました。これらを考えると導入時の懸念材料というのは執行部の決めつけに過ぎない、もしくは先入観によって判断を誤る可能性があるため注意が必要です。
ポイントは、最初は対面でもいいのでしっかりと意義を伝えること。そして、中身のコンテンツを作ること。この2点だと思います。なんでこのアプリを入れてほしいのか、今後組織としてこれで情報を発信することを伝えること。そして、アプリを使ってくださいと言っても「開くメリットがない。」となってしまうので、コンテンツの中身を常にしっかり作るということが大事かなと思います。
TUNAG利用のメリット
数字で見えるということと情報発信ができるということの2点が一番大きいと思います。情報発信は、やはり組合が何をしているかを見える化するというところに繋がると思います。見えないと「なんで組合費ってかかっているんですか」とか「組合費、高くないですか」という不満にも繋がりやすいので、しっかりと活動を見えるようにするというのは大事なことだと思います。要は、労働組合の価値を高めていかないと不満に繋がりやすいということです。組合費が何に使われているのか、どんな活動をしているのかを見える化してしっかり伝えていくことが執行部の果たすべき役割だと思います。労働組合の第一命題は「雇用の確保」と「労働条件の改善」なのでそれは当然やるとして、これに加えて今の時代の労働組合に求められるのは「情報開示」「活動の見える化」だと思います。また、先程の役員の話のようにバトンを受け取りたいと思ってもらうには、活動の魅力や良さ、労働組合の意義を知ってもらわないといけません。この部分がしっかりできれば、組合員の方の満足度も上がると思うので、今はこれが第一だと思っています。
更に弊組の場合は、組合活動に加えて会社の発信文書・情報も載せています。会社で出しているいわゆるお知らせ書面や文書、年末調整や各種手続きのお知らせ、社長の思いやパーパス、理念を伝える記事などを組合でいくつか抜粋させていただいて発信しています。他の組合さんでは、「会社は会社、組合は組合」というように線引きすることが多いと思うのですが、うちはそうではなくて、会社があっての組合活動だと思っているので、組合員に伝える必要があるものはしっかりと発信しています。このように会社のことも発信しているので、組合員ではないですが人事の方何人かはどういうものを投稿しているのかを見れるように権限を付与しています。重要な情報は労使共同、協力し、発信していくということを意識しています。
また、イオングループは災害の際のボランティアや木を植えるなどの社会貢献活動に力を入れています。こういった情報も労使協働の観点で、TUNAGで発信することにより、多くの方に情報が行き届くので活用の幅が広がると思います。
TUNAGによって得られた価値
TUNAGを入れて一番大きかったのは、組合活動に触れる接点を増やすことが出来たことです。今までは、レクリエーションに来る人は組合が好きな人、来ない人は興味がない人というような判断軸になってしまっていました。しかし、レクリエーションなど現地には来れないけど組合の情報は知りたいとか団体交渉・春闘でどんな交渉をしているのかを知りたいという方もいるので、そのようなニーズに応えられるようになったのは大きいのではないかなと思います。

次のアンバサダーへのメッセージ
アンバサダーをさせていただいて、改めてTUNAGの良さを認識する機会になりました。機能としてもそうですし、組織運営の考え方としてもそうです。また、自分の組織を見直す機会にもなりました。対外向けに講演や説明をさせてもらう機会も増えたので、自分の組合の振り返りにもなりました。
今後のアンバサダーの方は、TUNAGの運営を軸にきっと組合活動を良くしたいと思っている方々だと思います。その思いや自分の組織でされてきた取り組み内容、TUNAGの良さを対外的に伝えていただきたいと思います。活動を推進する上で、その想いや考え方を伝えることは重要だと思っていて、アンバサダーの方はなぜTUNAGを導入したのかとかTUNAGを導入して何が変わったのかという事例を積極的に伝えていく必要があると思います。その話を聞き、参考にすることで、自組織の課題や悩みが解消される組合は増えてくると思うので、そういう存在になっていただけるといいかなと思います。
〜佐々木様、ありがとうございました!〜