労働組合が満額回答を得るためのポイントは?賃上げ交渉の現状も紹介
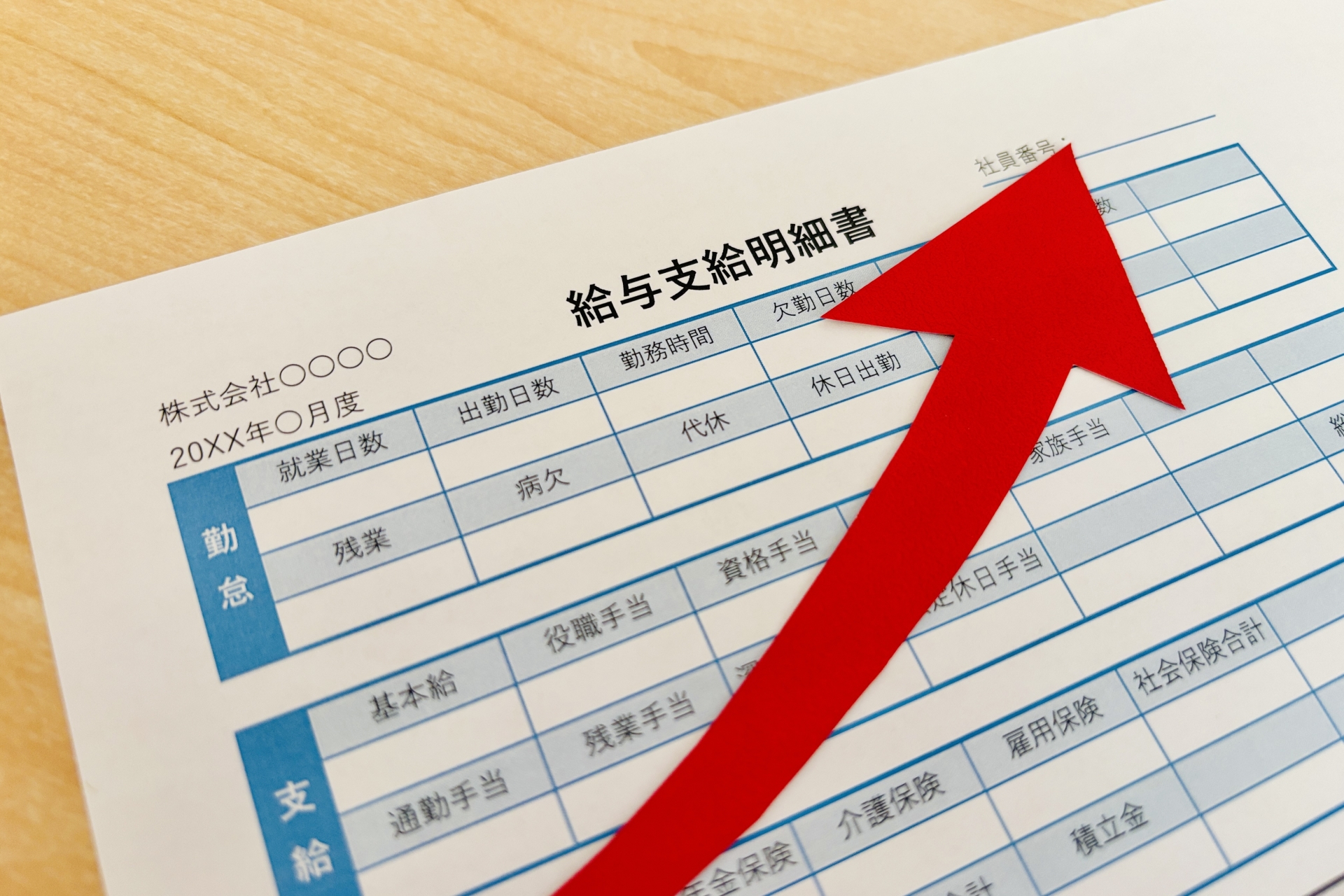
近年は春闘における大手企業の満額回答が相次いでいますが、労働者全体の給与水準の引き上げには結び付いていないのが実情です。異例の賃上げが続く背景と今後の課題、労働組合が満額回答を得るためのポイントについて解説します。
近年の賃上げ交渉の成果
春闘の結果をニュースでチェックしている人も多いのではないでしょうか。まずは、近年の賃上げ交渉の成果を見ていきましょう。
大手企業では満額回答が相次ぐ
2025年の春闘では、集中回答日の3月12日に満額回答が相次ぎました。自動車メーカーはトヨタとマツダが、大手電機メーカーはNEC・日立製作所・富士通が満額回答となっています。大手機械メーカーでも、三菱重工業・川崎重工業・IHIが満額回答です。
また、スズキと三菱ケミカルに至っては、組合の要求を上回る金額で妥結しています。満額に至らなかった大手企業も、高水準の回答が並びました。
労働組合の中央組織「連合」が公表している2025年春闘の第1回集計結果によると、ベアと定期昇給を合わせた平均賃上げ率は5.46%で、2年連続の5%超えとなっています。
出典:前年を上回る回答引き出し!中小組合も5%超え! 有期・短時間・契約等労働者(時給)の賃上げ率は6%超え! ~2025 春季生活闘争 第1回回答集計結果について~
中小企業は二極化が広がっている
2024年の春闘の賃上げ率は、最終的に全体で5.1%となりましたが、300人未満の中小企業に限ると4.45%にとどまりました。連合が集計を開始した1989年以降で最大の開きです。
2025年の春闘でも、大手企業と中小企業の賃上げ率には格差が見られます。中小企業においては、賃上げに応じる企業と応じることが難しい企業の二極化が広がっているのです。
連合は2025年の春闘で中小企業に「賃上げ率6%以上」を掲げていましたが、第5回回答集計結果を公表した2025年5月2日の時点では、5%をわずかに下回っています。
出典:33年ぶりの5%超え! ~2024春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果について~
出典:中堅・中小組合の健闘が続く! 短時間等労働者の時給引き上げ率は一般組合員を上回る! ~2025 春季生活闘争 第5回回答集計結果について~
異例の賃上げが続く背景と今後の課題
相次ぐ大手企業の賃上げは、歴史的な物価高に対する一時的な反応だと見る意見もあります。近年の春闘の成果を物価上昇による一時的な現象にしないことが重要です。
日本では労働者の約7割が中小企業で働いており、中小企業の継続的な賃上げが労働者全体の賃金水準の引き上げにつながります。
大手企業の賃上げの勢いを中小企業にも波及させるためには、コスト上昇分の適正な価格転嫁を取引先の中小企業に対して受け入れることが不可欠です。
労働組合が満額妥結を得るためのポイント
団体交渉で満額妥結を勝ち取るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。満額回答に向けて組合が意識すべき三つのポイントを紹介します。
入念な事前準備を行う
団体交渉で会社に要求する内容には、説得力を持たせる必要があります。公的な統計資料や業界団体の調査結果、賃金水準や労働時間などの基礎情報などを収集し、客観的なデータに基づく根拠を提示しましょう。
賃上げを要求する場合は、対応できるだけの支払い能力(余力)が会社にあるかどうかを確かめることも重要です。貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの財務データを入手した上で、専門家の力も借りながら経営側の支払い能力を見極めましょう。
組合員の声を集めて会社に提示するのも効果的です。要求の背景にある組合員のニーズや不安を示せるほか、より正確な賃金実態の把握にもつながります。
組合の交渉力を高める
労働組合の交渉力は、組合員の数が多いほど強くなります。日頃から積極的に勧誘を行い、一緒に活動する仲間を増やしましょう。
アルバイトやパートが多い職場なら、非正規職員も組合に加入できるように組合規約を変えることが重要です。人事にかかわる管理職以外は、基本的に誰でも組合員になれるため、規約で制限されていないか確認しましょう。
また、良好な労使関係が構築されていれば、会社の情報を得やすくなります。非上場企業の場合、基本的には会社の財務状況が公開されていないため、会社に情報提供を求めるか、現場の実感を頼るかしかないのが実情です。
労働組合法では情報提供の求めに会社が応じる義務を課しているものの、提供する内容は会社が自由に決められます。できるだけ詳細な情報を得るためにも、普段から会社と良好な関係を維持しておきましょう。
妥協点を見いだすことも必要
団体交渉は1回では終わらないケースも少なくありません。また、議論を重ねても満額回答に至らない場合も想定されます。
団体交渉で重要なのは一定の成果を出すことです。交渉がうまく進まない場合も、双方の主張を整理し妥当な範囲内で妥協点を見つけ、交渉を決裂させないようにしましょう。
交渉中は常に落ち着いた態度で対応することも重要です。感情的になると正しい判断ができなくなるため、冷静な対応を心掛けましょう。
満額回答を実現できる力をつけよう
近年は春闘において満額回答が相次いでいるものの、大手企業と中小企業の賃金格差はまだまだ埋まっていません。賃上げに応じる企業と応じられない企業の二極化が進んでいることも課題となっています。
団体交渉で満額回答を得るためには、入念な事前準備や組織力の強化が重要です。交渉がうまく進まない場合も、妥協点を見つけて一定の成果を目指すようにしましょう。












