労働組合として知っておきたい最低賃金法。法知識を基にした交渉のポイントも
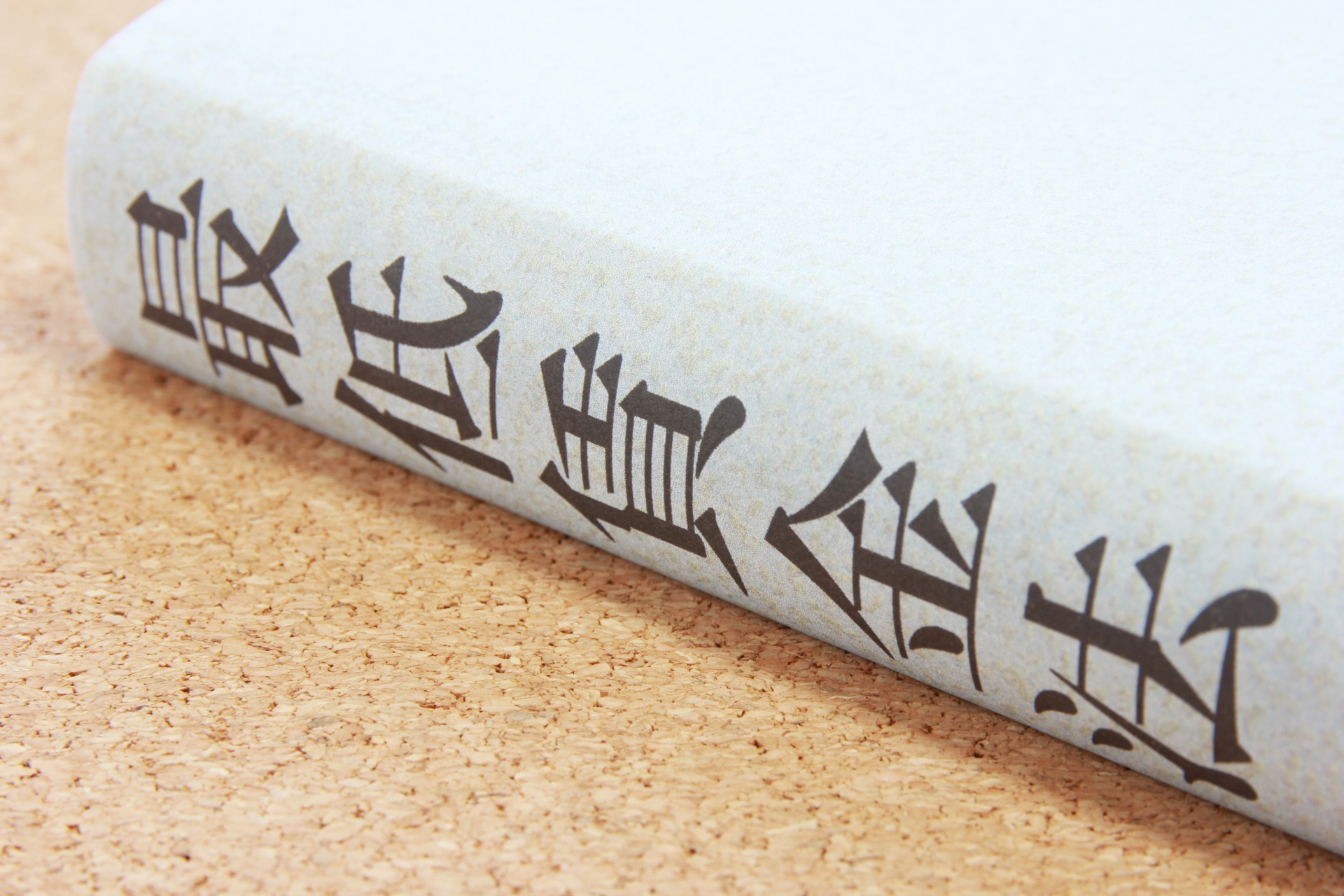
最低賃金法は、賃上げ交渉を検討している労働組合がしっかり押さえておきたい法律です。最低賃金法とは何なのか、概要から最低賃金の種類・決定のプロセスまで詳しく解説します。労働組合の活動と最低賃金法との結び付きや、法律の知識を交渉にどう生かすかも今後の参考にしましょう。
最低賃金法とは何か
労働組合の運営に当たって、理解が必要な法律は多くあります。その一つが、賃上げ要求にも関わる「最低賃金法」です。最低賃金法とは何なのか、最低限押さえておきたいポイントを分かりやすくまとめました。
最低賃金法の概要
最低賃金法は、第1条によると、労働条件の改善を図って労働者の生活安定・労働力の質的向上・事業の公正な競争・国民経済の健全発展を目的とした法律です。
使用者は、原則として最低賃金以上の賃金を労働者に支払う義務があります。違反した場合は罰則(50万円以下の罰金)が科される決まりです(同法第4条第1項・第40条より)。最低賃金法の保護を受ける人は、年齢・企業規模などを問わず、原則として全ての労働者です(同法第2条第1項、労働基準法第9条)。
複数の最低賃金が適用される労働者には、最も高い水準を適用することと定められています(最低賃金法第6条第1項)。
参考:最低賃金法 第1条・第2条第1項・第4条第1項・第6条第1項・第40条|e-Gov法令検索
「地域別」「特定(産業別)」最低賃金の違い
最低賃金法では、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」という2種類の最低賃金が定められています。
地域別最低賃金は都道府県単位で決まり、その地域における生活費や賃金の水準・事業の支払い能力などを基に定められる最低賃金です(最低賃金法第9条)。
特定(産業別)最低賃金は、特定の事業や職業に従事する労働者に適用されます。地域別最低賃金よりも高く設定しなければならない決まりです。(同法第15条第1項、第16条)
参考:最低賃金法 第9条・第15条第1項・第16条|e-Gov法令検索
最低賃金は誰がどう決めているか
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金では、決定のプロセスが違います。地域別最低賃金の改定は、厚生労働省の中央最低賃金審議会が目安を出し、それを基に都道府県労働局が地方最低賃金審議会を開催します。最低賃金審議会では労使で慎重に議論された上で決定する、2段階体制となっています。審議で考慮される要素は、その地域における「労働者の生計費」「賃金」「通常の事業の賃金支払能力」です。
特定(産業別)最低賃金は、関係労使からの申し出に基づき、労使および公益を含む三者構成(公労使三者構成)の審議会で審議され、その答申を受けて厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定・告示します。
参考:最低賃金法 第10条第1項・第12条・第15条第1項,第2項・第19条|e-Gov法令検索
労働組合と特定(産業別)最低賃金の関係
労働組合の活動と最低賃金法は、主に特定(産業別)最低賃金について深く関わっています。具体的にどのような結び付きがあるのか、特定(産業別)最低賃金が決まる要因を交えながら解説します。
特定企業の賃金水準は特定最低賃金に影響し得る
特定(産業別)最低賃金の改正を申し出る際には、企業内最低賃金の実績データが添付され、審議材料の一つとなります。添付資料に含まれる企業のうち最も低い水準が、特定最賃の引き上げ上限額として扱われる決まりです。
最も低い水準より著しく高い特定(産業別)最低賃金の引き上げは、労使の合意が得られず実現が難しくなります。つまり、企業別労働組合がうまく賃上げ交渉ができておらず、特定企業の企業内最低賃金が低い状態だと、特定(産業別)最低賃金の引き上げができないということです。
参考:「企業内最低賃金」の取り組みについて P.18|日本労働組合総連合会(連合)労働条件局
企業内最低賃金は労使協定で決められる
企業内最低賃金は、団体交渉や春闘などで組合と使用者が合意した上で、協定として定められます。連合の調査によると、全国で企業内最低賃金協定を締結している労働組合は約54%です。
連合や産業別労働組合は、協定水準の向上支援・見本協定の提示を通じて組合に対策を促しています。企業内最低賃金の協定の適用人数が多いほど、特定(産業別)最低賃金の審議材料として取り上げられる確度が高まるためです。
参考:「企業内最低賃金」の取り組みについて P.20〜21|日本労働組合総連合会(連合)労働条件局
最低賃金法の知識を生かした賃上げ要求のポイント
法律の知識を持っていても、実際の団体交渉に生かせなければ意味がありません。では最低賃金法のルールは、交渉の場でどのように役立てればよいのでしょうか。企業内最低賃金の労使協定を結ぶに当たって、必要な取り組みを二つ紹介します。
最低賃金法の内容を整理して資料を作る
まず最低賃金法の目的・対象・地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金という二つの最低賃金制度、異なる決定プロセス・適用ルールを整理しましょう。使用者側が最低賃金法の中身を正確に理解しているとは限りません。
特定(産業別)最低賃金の適用条件や、地域別最低賃金との優先順位(最低賃金法第6条第1項)も図示資料で分かりやすく示します。該当条項や条文の趣旨(目的)を添えることで、交渉資料が分かりやすくなって説得力が高まるでしょう。
組合員の生活実態について声を集めておく
企業内最低賃金の労使協定を結ぶに当たって、組合員の生活実態は賃金水準を上げるために重要な交渉要素です。賃金が低くなりやすい非正規雇用者・若年層などを中心に、賃金と生活の実態(生活費など)をアンケートやヒアリングで把握しましょう。定量的・定性的な情報どちらも収集しておくと、より交渉での説得力が増します。
例えば、組合員の生活費が地域別最低賃金を上回るという実態を数値で示すことで、「地域別最低賃金を上回っているのだから大丈夫だろう」という賃金設定では生活が成り立たないことを交渉の論拠にできます。こうしたデータとリアルな声から引き上げが必要な理由を伝えると、使用者側も検討しなければならないと思うはずです。
最低賃金法を理解して根拠ある賃上げ要求を
最低賃金法には二つの最低賃金が定められており、その決定プロセスも違って理解が難しいと思うかもしれません。ただ、最低賃金法の知識は、主に賃上げ交渉において交渉の説得力を高める材料になり得ます。
まず法律の趣旨を理解した上で二つの最低賃金の違い、労働組合との関係を把握しましょう。企業内最低賃金の労使協定締結や賃上げ交渉に活用できるよう、理解した最低賃金法の内容は整理しておくことをおすすめします。












