産業別組合とは?日本における特徴や歴史、求められる役割を解説
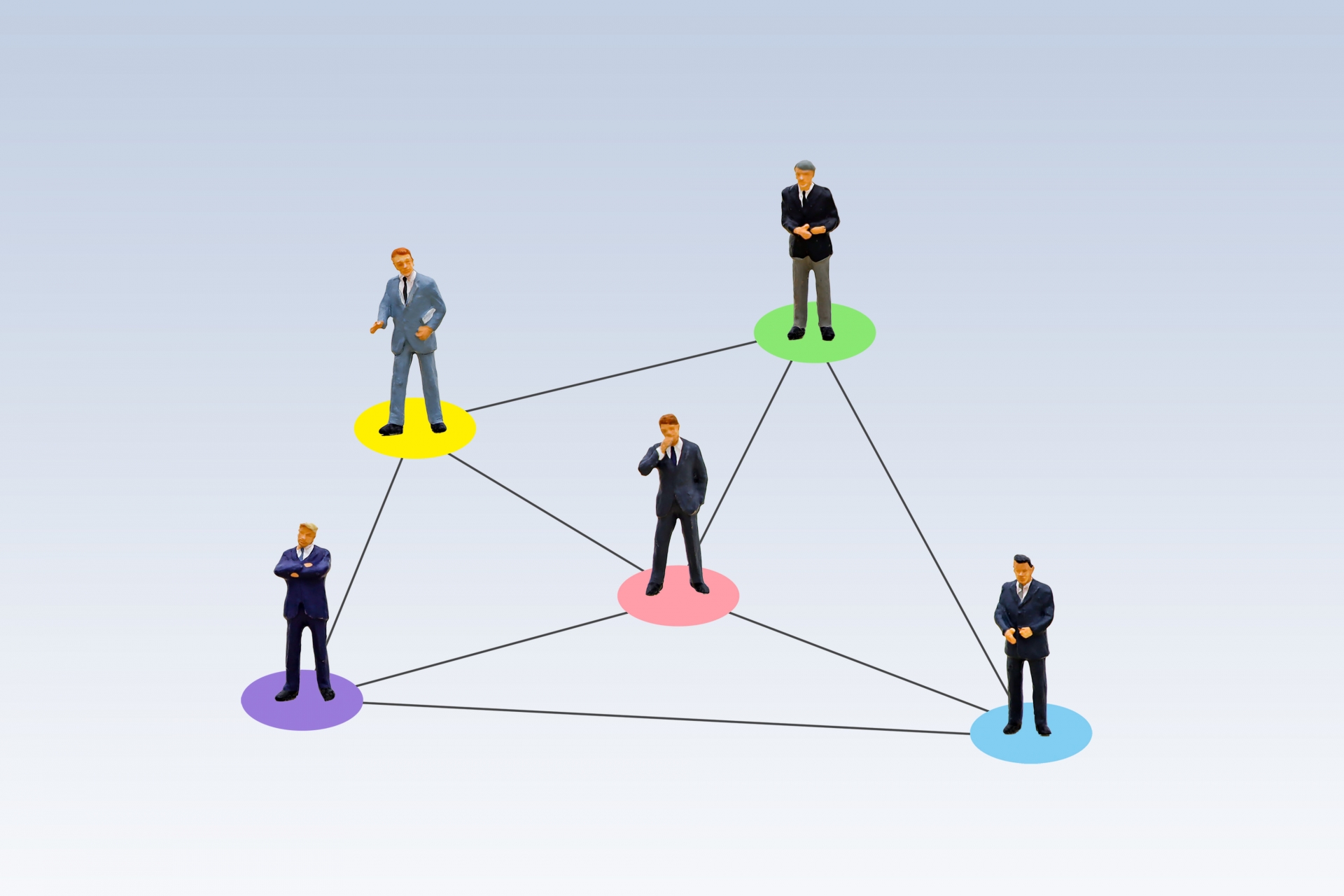
産業別組合とは産業ごとに組織された労働組合のことであり、日本は欧米と違い企業別組合が発達してきました。春闘の統一要求や労働協約の地域的拡張適用において、産業別組合の存在意義が示されます。産業別組合の特徴や歴史を見ていきましょう。
産業別組合の基礎知識
労働組合といえば各企業にある組織をイメージしがちですが、他にもさまざまな種類があります。主な種類や日本の労働組合の特徴、産業別組合の歴史を紹介します。
労働組合の主な種類
組織としての労働組合は、組合構成員により次の3種類に区別されます。
- 単位組織組合:個人が構成員となり、支部などの下部組織がない
- 単一組織組合:個人が構成員となり、内部に支部などの下部組織がある
- 連合団体:単位組織組合や単一組織組合で構成される労働組合
また、労働組合には次のような種類もあります。
- 企業別組合(単位組合):特定の企業で働く労働者により構成される
- 産業別組合(産業別組織):特定の産業に属する複数の企業の労働者で構成される
- ナショナルセンター:国内の複数の労働組合を統合した全国的な組織
- ITUC(国際労働組合総連合):世界各国のナショナルセンターを束ねる国際的な連合体
どのような形の労働組合であっても、より良い労働環境を求めて労働者が団結するという意味では同じです。
日本の労働組合の特徴
欧米諸国では産業別組合が発達しているのに対し、日本の労働組合は企業別組合が中心です。企業別組合の組合員は、労働組合員としての側面と同じ企業内の従業員という側面を併せ持っており、企業別の意識が強い特徴があります。
一方、欧米諸国の労働組合員は企業別の意識がそれほど高くなく、転職先が同じ産業なら労働組合を脱退する必要もありません。産業ごとに組合がまとまっているという意識が強いのです。
日本の場合は退職すると労働組合も脱退する必要があるため、転職を繰り返す場合は組合に入るメリットが大きくありません。人材の流動性が高くなりつつある日本では、労働組合の存在意義が揺らいでいるといえます。
産業別組合の歴史
産業革命で先行していた18世紀半ばごろの英国で、労働組合が世界で最初に結成されました。19世紀半ばごろまでには全国規模の産業別組合に発達し、資本家との賃金交渉を行っています。
日本では明治時代から労働組合のような組織がありましたが、現在主流の企業別組合が発展していったのは第二次世界大戦後です。終身雇用と表裏一体で発達し、労使協調の基盤となって高度経済成長を支えました。
日米英で労働組合の組織率が下がっているのとは対照的に、北欧やドイツでは今でも大規模産業別組合が健在です。組合の代表が経営に参画する従業員代表制も定着しており、労働組合が大きな存在感を示しています。
日本の代表的な産業別組合
日本の代表的な産業別組合は次の通りです。
- 自動車総連:自動車産業を中心に、自動車部品メーカーや関連産業の労働組合で構成
- 電機連合:電気機械器具製造業や情報通信業などの労働組合で構成
- UAゼンセン:繊維・化学・医薬・卸小売・宿泊・飲食サービスなどの労働組合で構成
- JAM(ものづくり産業労働組合):機械・金属産業を中心とした製造業の労働組合で構成
- 基幹労連:鉄鋼・造船・重機などの基幹産業の労働組合で構成
- 電力総連:電力産業および関連産業の労働組合で構成
- 情報労連:情報通信産業の労働組合で構成
上記以外にもさまざまな産業で産業別組合が組織されています。
産業別組合の存在意義や役割
日本においては、春闘の統一要求や労働協約の地域的拡張適用で、産業別組合が存在感を放っています。産業別組合の存在意義や役割を見ていきましょう。
春闘で統一要求を掲げる
春闘とは、労働組合が毎年春に、賃上げや労働条件の改善を求めて企業と交渉する運動のことです。同一産業内で組合が連携することで交渉力を高めているのが特徴です。
春闘では産業別組合が中心となり、それぞれの要求を統一要求として掲げ、企業別組合は所属する産業別組合の統一要求を基に企業ごとの要求を検討します。産業別組合の統一要求は、中小を含む産業全体の賃金相場に影響します。
例えば2025年の春闘では、自動車総連が賃上げ要求の目安として月1万2,000円、UAゼンセンは正社員のベースアップと定期昇給で6%基準を掲げました。
一つの労働協約が同一産業内で適用される
労使間の団体交渉で決定した内容は、労働協約として適用されますが、原則として組合員にしか適用されません。ただし、特定の地域において同種の労働者の約3/4以上が一つの労働協約の適用を受けている場合、組合に属さない従業員にも同じ労働協約が適用されます。
例えばUAゼンセンでは、大型家電量販店で働くフルタイム勤務の従業員が、年間所定休日数の最低日数を111日以上とする労働協約の地域的拡張適用を受けています。適用地域は青森県・岩手県・秋田県の全域、適用期間は2023年6月1日~2025年5月31日です。
出典:連合|より良い職場づくりポータル – 労働協約って何?
産業別組合の特徴や役割を理解しよう
日本では独自の企業別組合が発達してきた歴史があり、欧米諸国のように産業別組合をメインとした活動があまり見られません。ただし、春闘の統一要求や労働協約の地域的拡張適用など、産業別組合が存在感を示すケースもあります。
労働組合として産業別組合の特徴や役割を理解し、今後の組合活動に生かしていきましょう。












