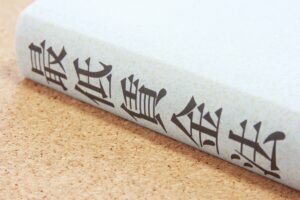労働組合の中で「企業内組合」はどのような立ち位置?意義や強みを解説

組合を次世代につなぐため、企業内組合の意義や強みを若い組合員に伝えたいと思っている労働組合もあるかもしれません。企業内組合の定義や位置付け・法的に満たすべき要件といった基本、企業内組合ならではの強み、存在意義を次世代に伝えるポイントを解説します。
労働組合の1つ「企業内組合」の基本
若手や新しく参加した組合員に企業内組合について説明するためにも、労働組合として企業内組合の定義や立ち位置を把握しておきましょう。定義と法的要件と注意点、ほかの形態の労働組合とどう違うのかを解説します。
企業別に組織される労働組合
企業内組合とは、特定の企業の従業員だけで構成される労働組合です。日本では主流の形態となっています。欧米諸国では産業別組合が主流であり、企業単位での労働組合が主流となっている点は日本の特徴です。
企業内組合は、終身雇用・年功賃金・企業内教育などの制度との親和性があります。労働者が企業とともに長期的な関係を築く前提で、発展してきました。
法的要件を満たさなければ認められない
企業内組合に限らず、労働組合には労働組合法第2条・第5条に要件が定められています。労働組合として法的に認められるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 労働者が主体となって組織していること(主体性)
- 労働条件の維持改善を主たる目的とすること(目的)
- 使用者から独立していること(自主性)
- 所定の必要事項を定めた組合規約を整備していること(規約)
法的要件を満たしていない組合(いわゆる法不適合組合)でも、団体交渉を申し入れること自体は可能です。しかし、団体交渉を拒否されない・組合への参加を理由に不利益的な取り扱いをされないなど、労働組合法上の保護は受けられません。
「御用組合」とは異なる
企業内組合は、労働組合法上の要件をしっかりと満たした正式な労働組合であり、企業との団体交渉の権利が保障されています。使用者の不当労働行為があれば、労働委員会に申し立てることもできます(労働組合法第7条・第27条第1項)。
一方、労働組合が企業側の意向を過度に反映している場合、いわゆる「御用組合」として自主性を欠くと見なされます。労働組合法第2条のただし書きにより、以下のような団体は労働組合法上の「労働組合」として認められません。
- 組合役員に監督的地位にある労働者(管理職等)が含まれる
- 組合の運営資金に対して使用者から経済的援助を受けている
企業内組合の運営においては、特に運営資金に対しての経済的援助を受けてしまっていないかに注意しましょう。例えば組合員が就業時間中に組合活動に当たったとき、その時間についても賃金を受け取ると、「組合運営に経済的援助を受けた」と見なされる場合があります。
参考:労働組合法 第7条・第27条第1項|e-Gov法令検索
ほかの労組形態との違い
労働組合には企業内組合のほかに、合同労組(地域ユニオン)・産業別組合・ナショナルセンターなどがあります。
合同労組は特定の企業に属さず、地域や職種をまたいで組織され、個人加盟も可能です。産業別組合は、同一産業に属する複数の企業の労働組合で構成されます。ナショナルセンターは産別組織の全国統括団体です。日本では連合、全労連などが該当します。
本来、企業との交渉は企業内組合の役割です。ただ産業別労働組合や合同労組も企業との交渉に入ることがあり、役割が重なる場面も少なくありません。春闘などでは産業別組合が主導し、加盟する企業内組合の交渉に方針を与えることが多いようです。
企業内組合が持つ交渉力の強み
労働組合には企業内組合のほかにも形態があります。では企業内組合特有の強みとは、具体的に何なのでしょうか。それは「交渉相手が自らの勤める企業である」ことです。詳しい内容を見ていきましょう。
現場に精通していて課題が把握しやすい
企業内組合の場合、組合役員は職場経験者であることがほとんどです。交渉相手である企業への情報感度が高いため、改善提案が現実的かつ説得力を持ちやすくなります。
企業内組合の役員や組合員は企業内部の人間という点で、合同労組や産業別組合が介入してくるよりも企業側が警戒しにくいのも強みです。職場や従業員からの信頼を基にした交渉がしやすくなります。
また、労働組合の人員も企業に属しているため、最終的に目指すところは経営サイドと一致しやすいでしょう。労働条件についての不満があったときも、対立というよりは企業の利益を最大化して自分たちにも還元されるような交渉が可能です。
企業との協調関係が改善提案を後押しする
企業内組合は合同労組や産業別労働組合に比べて、対立ではなく建設的な関係を目指しやすい点も大きな強みです。従業員の定着や生産性の向上といった企業側のメリットも、自分事として説得力のある説明材料になります。
例えば勤務間インターバルの設置や福利厚生の見直しなどの要求は、労働環境の改善だけでなく組織エンゲージメントの向上にもつながることです。結果として人材の定着が進み離職率が下がれば、組合員(役員)が働きやすい環境が整っていきます。
全く自社に関係のない労働組合から「御社にとってもメリットがある」と言われても、企業は要求を通すために言っているとしか思わないでしょう。しかし企業内組合から同じことを言われた場合、組合員自身のメリットにもつながることが分かるため、企業としても要求を受け入れやすくなります。
労働組合内で企業内組合の意義を伝えるには
これからの世代を担う組合員や役員候補には、企業内組合の意義を伝えていく必要があります。そのために労働組合ができることは、客観的な情報の可視化・共有と役員間での認識統一です。
制度的な根拠や改善実績を資料で可視化する
次世代の組合員に企業内組合の意義を理解してもらうには、まず労働協約の内容や団体交渉の記録を可視化しましょう。労働組合法に定められた要件や、改善の実績も資料に盛り込むとより理解が進みます。
若手や加入したばかりの組合員にも、分かりやすく伝える工夫が必要です。紙のパンフレットやメールではなかなか見てもらえないという場合は、労働組合向けのアプリ「TUNAG for UNION」を活用する方法があります。スマホから手軽にアプリで情報をチェックできるため、共有がしやすくなるでしょう。
労働組合向けアプリ – TUNAG for UNION|情報共有、申請手続きをペーパーレス化
役員間で説明内容の共通認識を持つ
組合員に企業内組合の存在意義を正しく伝えるには、役員間で共通認識を持っていることが前提となります。役員によって認識がバラバラだと、「言っていることが前回の説明会と違う」と教わる側が混乱しかねません。
学習会や打ち合わせを積極的に実施し、役員の知識・説明スキルを底上げした上で、企業内組合の意義について共通の認識をつくりましょう。企業内組合の意義がしっかりと伝われば、組合を次世代へ継承する基盤ができていきます。
企業内組合の意義を伝えて次世代につなごう
企業内組合は労働組合の形態の1つです。労働組合法に定められた要件をしっかり満たす限り、「御用組合」とは違って独立した労働組合として法の保護を受けられます。労働組合には合同労組や産業別組合などほかの形態もありますが、組合役員や組合員が企業の一員という点が企業内組合の強みです。
次世代に引き継いでも労働者を守れる組合であり続けるには、企業内組合の意義や強みを若手にしっかり伝えていく必要があります。役員間でも認識を統一しつつ、将来的にも意義のある企業内組合であるために情報を共有していきましょう。