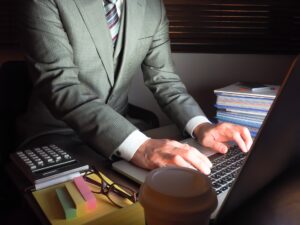フレックスタイム制とは?労働組合が押さえておくべきポイントを解説

会社がフレックスタイム制を導入するためには、労使協定を結ぶ必要があります。提示されたルールを労働組合として適切にチェックできるよう、制度の内容を理解しておきましょう。フレックスタイム制について押さえておくべきポイントを解説します。
フレックスタイム制の基礎知識
働き方の多様化を求められる中、フレックスタイム制を導入する企業が増えています。具体的にどのような制度なのか、類似する働き方の違いと併せて見ていきましょう。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定期間の総労働時間を定めた上で、その範囲内で従業員が始業・終業時間を自由に決められる制度です。
従業員が自分のペースで効率的に働けるため、生産性の向上が期待できます。仕事とプライベートを両立しやすくなったり、通勤ラッシュを避けて出勤できたりすることもメリットです。
フレックスタイムを導入する場合は、労使協定の締結と就業規則などへの記載が必要です。労使協定では、対象となる労働者の範囲や清算期間、標準となる1日の労働時間などを定めます。
フレックスタイム制と相性が良い業界や職種
個人の裁量で仕事を進めやすい業界や職種は、フレックスタイム制と好相性です。具体的には、情報通信業・研究職・企画職・営業・クリエイティブ職などが挙げられます。
逆に、サービス業・接客業・製造業・医療・介護といった業界や職種は、フレックスタイム制と相性が悪いといえるでしょう。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、フレックスタイム制を採用している企業の割合は7.2%です。企業規模が大きくなるほど割合も大きくなっており、企業規模1,000人の企業の割合は34.9%と、全体の平均を大きく上回っています。
変形労働時間制や裁量労働制との違い
変形労働時間制とは、業務の実態に合わせて労働時間を柔軟に調整する制度です。忙しいときと暇なときがある場合に、労働時間に偏りを持たせることで無駄な労働を減らせます。
フレックスタイム制は変形労働時間制の一種です。ただし、変形労働時間制が企業として合理的な労働を実現する制度であるのに対し、フレックスタイム制は従業員の希望を重視するという違いがあります。
また、裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なくあらかじめ定めた時間を労働時間とみなす制度です。実際の労働時間がみなし労働時間を超えた場合、原則として残業代は発生しません。
フレックスタイム制の導入時に労使で定める事項
フレックスタイム制の導入時には、以下に挙げる項目について、労使間で検討する必要があります。それぞれの具体的な内容を押さえておきましょう。
対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制の導入を検討する場合、適用させたい従業員の範囲は、さまざまなパターンが考えられるでしょう。制度の対象にできる労働者の範囲に制限はありません。
全従業員に適用させることも、また特定の部署・職種・個人を対象とすることも可能です。パートやアルバイトも、労使協定で対象と定めれば、フレックスタイム制を適用できます。
清算期間
フレックスタイム制の清算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。2019年4月の法改正以前は上限が1カ月でしたが、現在は最長3カ月まで延長されています。
清算期間を検討する際はその長さだけでなく、起算日も定めなければなりません。また、清算期間が1カ月を超える場合は、所轄の労働基準監督署長の届け出が必要です。
清算期間における総労働時間
清算期間における総労働時間とは、労働者が清算期間内に労働すべき時間として決められた時間のことです。いわゆる所定労働時間を指します。
清算期間内で労働者は始業・終業時刻を自由に決められますが、清算期間内の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないように調整する必要があります。
清算期間における総労働時間の上限の計算式は次の通りです。
清算期間の暦日数/7日×1週間の法定労働時間(40時間)
例えば、清算期間の暦日数が30日の場合、法定労働時間の総枠は171.4時間になります。
標準となる1日の労働時間
清算期間における総労働時間を期間中の所定労働日数で割った時間が、標準となる1日の労働時間です。年次有給休暇の取得時の賃金を算定する際に用いられます。
フレックスタイム制の対象者が年次有給休暇を1日取得した場合、標準となる1日の労働時間を労働したものとして取り扱わなければなりません。
コアタイム・フレキシブルタイム
フレックスタイム制におけるコアタイムとは、従業員が1日のうちで必ず勤務しなければならない時間帯のことです。一方、フレキシブルタイムは、従業員が自由に始業・終業時間を設定できる時間帯を指します。
コアタイムは必ず設定しなければならないものではありませんが、設定する場合は開始・終了時刻を協定で定めなければなりません。また、「コアタイムがある日とない日がある」「日によってコアタイムの時間が違う」など、柔軟な設定が可能です。
なお、コアタイムが長すぎたりフレキシブルタイムが短すぎたりすると、フレックスタイム制の本来の趣旨に反することになります。
フレックスタイム制の残業について
企業が従業員に残業をさせる場合、労使間で36協定を締結しなければなりません。36協定を結んでいなければ、そもそも法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることは違法になるのです。このことを前提として、フレックスタイム制の残業について解説します。
フレックスタイム制の残業代
フレックスタイム制における残業の基準は清算期間です。清算期間が終了した時点で法定労働時間を超えた労働があった場合、その労働時間分の残業代を支払う必要があります。
従って、フレックスタイム制の36協定では1日の延長時間を協定する必要はなく、1カ月や1年の延長時間を協定します。
なお、フレックスタイム制で法定休日に働いた場合、その労働は清算期間における総労働時間や時間外労働とは別のものとしてカウントしなければなりません。また、法定休日に労働した時間であることから、35%以上の割増率で計算した賃金の支払いが必要です。
清算期間が1カ月を超える場合の残業代
清算期間が1カ月を超える場合は、1カ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間が残業時間となります。つまり、36協定を締結していないケースでは、フレックスタイム制において1カ月ごとに1週間当たり50時間を超えて働かせることはできません。
さらに、清算期間を通じて法定労働時間の上限を超えて労働した時間があった場合、その時間も残業時間になります。ただし、この残業時間には1カ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間を含みません。
フレックスタイム制の残業時間の上限規制
36協定を締結していれば、いくらでも残業させられるわけではありません。36協定で規定できる残業時間の上限は、月45時間・年360時間です。ただし、特別な事情がある場合は、残業時間の上限を延長できる特別条項の制度を適用できます。
36協定の特別条項を設けた場合、残業時間の上限は「年720時間・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」かつ「月100時間未満(休日労働を含む)」です。また、月45時間を超えられるのは年6カ月までとなっています。
フレックスタイム制を正しく理解しよう
フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間の範囲内で、始業・終業時間を従業員が自由に決められる制度です。働き方改革の一環として採用する企業が増えています。
フレックスタイム制を導入する場合は、労使協定の締結が必要です。労働組合として適切に対応できるように、制度の内容を細かく理解しておきましょう。